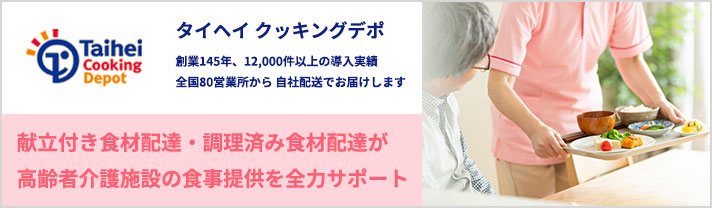- 投稿日 2025/09/26
- 更新日 2025/09/26
車いす駐車場の正しい使い方と守るべきマナーとは?思いやりが広がる使い方
個人旅行向け
障がい者施設様向け
高齢者施設様向け
付き添い
知識

車いすマークが描かれた駐車場、実は誰でも使っていいわけではありません。
本当に必要な人のためのスペースであり、正しく理解して利用することが求められます。
本記事では、対象者の範囲や申請制度、広いスペースが必要な理由、不適切利用の問題点などを分かりやすく解説します。
日常でできる思いやりある行動も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
車いすマーク駐車場の意味と対象者
車いすマーク付きの駐車場は、障がい者や高齢者など移動に配慮が必要な人のためのスペースです。
誰が利用できるのか、正しく理解しましょう。
車いすマークが示すものとは
車いすのマーク、正式には「国際シンボルマーク(International Symbol of Access)」と呼ばれ、障がいのある方への配慮がなされている施設や設備を示すために世界共通で使われています。
日本では、駐車場の優先スペースやトイレ、エレベーターなどに多く表示されており、「ここは移動に困難を感じる方が優先して使える場所である」という目印として認識されています。
ただし、このマーク自体に法的な強制力はなく、あくまで“思いやり”や“配慮”の象徴です。
誰が使える?高齢者や妊婦も対象?
車いすマークの駐車場は、基本的には歩行や移動に支障がある方を対象としています。
具体的には、車いすを常用している障がい者はもちろん、杖を使って歩行する高齢者や、妊娠後期の妊婦、けがなどで一時的に移動が困難な人も含まれます。
ただし、誰でも自由に使えるわけではなく、各自治体が運用する「パーキング・パーミット制度」に基づいた利用が推奨されています。
対象者の範囲や利用条件は自治体によって異なるため、事前に確認することが重要です。
パーキング・パーミット制度の概要と申請方法
車いすマーク付きの駐車場を適切に利用するためには、パーキング・パーミット制度の理解と申請が重要です。
制度の内容と手続き方法を解説します。
制度の仕組みと目的
パーキング・パーミット制度とは、障がいや高齢、妊娠などで移動に配慮が必要な人が、適切に駐車スペースを利用できるようにするための認証制度です。
自治体によって名称は異なりますが、全国の多くの地域で導入が進んでいます。
対象者には駐車場のフロントガラスなどに表示できる「パーミット(許可証)」が発行され、それをもって専用または優先スペースを使用できる仕組みです。
この制度は、思いやりだけに頼るのではなく、制度として公平に利用機会を確保することを目的としています。

申請の流れと必要書類は?
申請方法は自治体によって若干異なりますが、多くの場合は次のような流れです。
- 1 自治体の福祉課や道路交通課に申請書を提出
- 2 必要に応じて、医師の診断書や障害者手帳のコピーを添付
- 3 審査後、対象者にパーミット証が郵送されるか窓口で交付
申請に必要な書類には、本人確認書類、診断書または障害者手帳、申請理由書などがあります。
一時的なケガによる移動制限でも発行される場合があり、対象範囲は意外と広いため、まずはお住まいの自治体の公式情報を確認してみることが大切です。
なぜ広い駐車スペースが必要なのか
車いすマークのある駐車スペースが通常より広く設計されているのには、明確な理由があります。
ここではその理由を具体的に解説します。
動作のしやすさ:乗降・車いす展開の視点から
車いすユーザーが車に乗り降りする際、通常の駐車スペースの幅では不十分なことが多くあります。
まず、車のドアを大きく開ける必要があり、さらに車いすを車外に出して展開するためには、車の側面に十分なスペースが必要です。
また、介助者がいる場合は、車両の両側に移動スペースが必要になることもあります。
このような動作を安全かつスムーズに行うためには、標準の駐車スペースよりも広い幅を確保することが不可欠なのです。
これは単なる「快適さ」ではなく、「必要性」から生まれた設計です。

安全への配慮と空間の重要性
車いす利用者にとって、狭い駐車スペースは安全上のリスクを高める要因になります。
たとえば、隣の車にドアがぶつかることで車いすの出し入れが困難になったり、足元が狭いために転倒の危険性が増すこともあります。
また、雨天時や夜間など視界が悪い状況では、スムーズな動線が確保されていないと重大な事故につながりかねません。
広いスペースは単に利便性を高めるだけでなく、利用者の安全を守るための最低限の配慮として必要不可欠なものです。
駐車場に関する法制度とガイドラインの違い
車いす駐車場には「専用」と「優先」があり、法制度とガイドラインの扱いも異なります。
その違いを整理して理解しましょう。
道路交通法やバリアフリー法との関係
日本の法律において、車いすマークがついた駐車場の利用を直接的に罰則で規制しているものはありません。
道路交通法では駐停車禁止区域などの規定はあるものの、「優先駐車スペース」を不正利用した場合の罰則は原則存在しないのです。
一方で、「高齢者・障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」は、施設管理者に対して駐車場のバリアフリー化を求めています。
つまり、利用者への義務ではなく、施設提供者への努力義務として位置づけられているのが現状です。
「専用」と「優先」の違いと現場での扱い
駐車場には「専用」と「優先」という2種類の表示があります。
「専用駐車場」は、障害者手帳やパーキング・パーミットを持つ方のみが利用できるスペースで、施設側が管理ルールとして定めています。

一方、「優先駐車場」は法的拘束力は弱く、誰でも停められてしまう現状がありますが、本来は「必要とする人を優先するためのスペース」です。
現場ではこの違いが十分に理解されておらず、利用者間のトラブルや誤解を生む要因となっています。
利用者一人ひとりの理解と配慮が欠かせません。
利用が不適切な事例とその影響
車いす駐車場の不適切利用は、必要とする人の生活を大きく妨げます。
実際の困りごとや心理的な影響を具体的に見ていきましょう。
本当に必要な人が困るリアルなシーン
たとえば、商業施設や病院で車いす駐車場がすでに埋まっていた場合、車いすユーザーや高齢者は通常の狭いスペースに駐車せざるを得なくなります。
結果として、車からの乗り降りに非常に時間がかかり、場合によっては車いすを展開できず利用を断念することもあります。
特に雨の日や混雑時には、この影響は深刻です。
また、目的地にたどり着けなかったり、介助者に大きな負担がかかるケースも多く報告されています。
このように「少しの不適切利用」が当事者にとっては大きな障壁となるのです。
当事者の心理的負担と社会的な波及
不適切な利用は、物理的な不便さだけでなく心理的な負担をも生みます。
必要なスペースが使えない状況が繰り返されると、「また停められないのではないか」という不安や、「自分は歓迎されていないのでは」という疎外感につながります。
こうした経験は、外出の意欲を削ぎ、生活の質を下げる原因になります。
さらに社会的には、周囲の人々の無理解や配慮不足が浮き彫りになり、信頼や共感の欠如を広げてしまう可能性があります。
駐車場の使い方は、社会全体の思いやり意識を映す鏡とも言えるのです。
誰もができるマナーと共感アクション
車いす駐車場の適切利用を広げるには、一人ひとりの小さな行動が大切です。
日常でできる配慮と社会全体に広げる工夫を紹介します。
具体的な配慮行動の例
車いす駐車場を正しく守るためにできることは、決して難しいものではありません。たとえば、
- 「自分が対象者でない限りは駐車しない」
- 「一時的な停車でも使わない」
- 「必要そうな人を見かけたら譲る」
といった基本的な配慮が重要です。
さらに、駐車場内ではドアの開閉や通路の確保に気を配り、周囲の人に不便をかけないよう心がけましょう。
小さな意識の積み重ねが、誰もが安心して利用できる空間を作ります。
地域や社会に伝える啓発のアイデア
車いす駐車場の適切利用を広めるには、地域や社会全体での啓発が欠かせません。
たとえば、自治体や商業施設が掲示板やポスターで周知することは効果的です。また、学校教育の一環として「バリアフリーや思いやり」をテーマに学ぶ機会を作れば、未来の世代に意識を根付かせることができます。
さらに、SNSを通じて正しい情報やエピソードを共有することも身近な啓発方法です。
日常に寄り添った工夫が、社会全体の理解と共感を広げる第一歩となります。
車いす駐車場を取り巻く社会的課題と改善への動き
車いす駐車場をめぐっては、現場での不適切利用や制度の周知不足など課題が残ります。
改善に向けた動きや海外事例も見てみましょう。
公共施設・商業施設での現場課題
病院や市役所、ショッピングモールなど、多くの人が訪れる場所では車いす駐車場の需要が高まります。
しかし実際には「台数が少なく常に埋まっている」「優先スペースが遠く使いにくい」といった声が当事者から多く寄せられています。
また、施設管理側も「不適切利用を注意しにくい」という課題を抱えており、現場での対応が追いついていないのが実情です。
制度や表示があっても運用が徹底されなければ、本当に必要な人が恩恵を受けられません。
現場の改善努力と利用者の理解が両輪となることが求められます。
海外事例との比較と日本の今後
海外では、車いす駐車場の不適切利用に対し厳しい罰則を設けている国も少なくありません。
たとえば欧米の一部では、不正利用に高額の罰金を科すことで抑止力を働かせています。
また、監視カメラや市民通報制度を整備し、社会全体でルールを守る仕組みを作っています。
一方、日本では法的拘束力が弱く、モラルやマナーに依存しているのが現状です。
今後は制度の周知とともに、ルールを担保する仕組みを取り入れることで、利用環境の改善が進むことが期待されます。
車いす駐車場に関するよくある質問(FAQ)
車いす駐車場を利用する際、対象やルールに迷う人も多いはず。ここではよくある質問を取り上げ、分かりやすく答えていきます。
対象者でない家族が運転しても利用できる?
対象者本人が同乗している場合であれば、家族が運転して車いす駐車場を利用することは可能です。重要なのは「誰が運転するか」ではなく、「誰がその駐車場を必要としているか」という点です。
ただし、本人が同乗していないのに家族だけで使うことは不適切です。例えば「あとで本人を迎えに行くから」という理由で利用するのは、本当に必要な人が使えなくなる可能性を高めてしまいます。
利用条件を正しく理解し、必要な時にのみ活用することが大切です。
短時間の停車や荷物の積み下ろしは許される?
「ほんの数分だから」という理由での停車や荷物の積み下ろしは、原則として控えるべきです。短時間であっても、その間に必要な人が駐車できず困るケースが発生します。
特に病院や公共施設では、数分の差が当事者にとって大きな不便やストレスにつながります。
もしどうしても近くで荷物を降ろしたい場合は、係員に相談する、他の場所で対応するなど代替手段を検討しましょう。
車いす駐車場は「緊急時の一時利用場所」ではなく、常に優先すべき人のためのスペースです。
台数が不足していると感じたらどうすればよい?
多くの施設では、利用者の声をきっかけに駐車場の改善が検討されます。
もし車いす駐車場の不足を感じた場合は、施設管理者や自治体に意見を届けることが重要です。
具体的なエピソードを交えて要望を伝えると、改善につながりやすくなります。
また、地域のバリアフリー施策に関する協議会や市民意見募集に参加するのも有効です。
声を上げることで利用環境は少しずつ整っていきます。
利用者自身や家族、介助者が積極的に発信することが改善の第一歩となります。
大切なのは “思いやり” の気持ち

車いす駐車場は、誰かの移動や暮らしを支える大切なインフラです。
しかし制度やルールだけではなく、一人ひとりの「思いやりの気持ち」があってこそ、本当に必要な人に安心して利用してもらえます。
この記事で紹介した制度やマナーをきっかけに、まずは自分の行動を見直し、周囲へ正しい情報を伝えてみてください。
小さな配慮が社会全体の優しさにつながります。ぜひ関連記事もあわせてご覧いただき、理解をさらに深めてください。