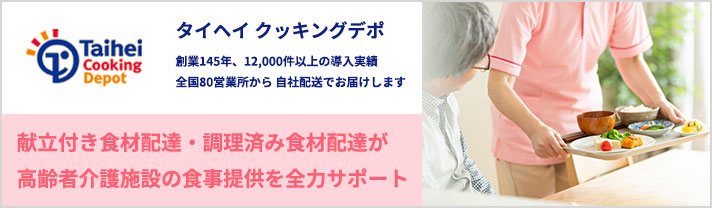- 投稿日 2025/06/12
- 更新日 2025/08/01
心のバリアフリー認定制度とは?制度内容と活用方法をわかりやすく解説
障がい者施設様向け
知識

高齢者や障がいのある方が安心して旅行できる環境づくりを目指して、観光庁が創設した「心のバリアフリー認定制度」。この制度では、物理的なバリアフリーに加えて、思いやりある接遇や情報発信といった“心の配慮”が評価の対象となります。
今回は、制度の基本情報から認定の取得方法、実際の認定施設の取り組み、そして制度を活用して安心・安全に旅行を楽しむ方法までをわかりやすく解説します。施設の旅行担当の方も、旅行を企画する方も、ぜひ参考にしてみてください。
目次
心のバリアフリー認定制度とは?
観光庁が創設した「心のバリアフリー認定制度」は、ハード面の整備だけでなく、接遇や情報発信といった“心の配慮”を重視する認定制度です。制度が生まれた背景やその目的、そして“心の”バリアフリーが意味するものについて、まずは基本から確認していきましょう。
制度の目的と創設背景
「心のバリアフリー認定制度」は、2020年のバリアフリー法改正をきっかけに、観光庁によって創設されました。この制度の目的は、高齢者や障がいのある方が安心して旅行を楽しめる環境を整えることにあります。
従来は設備面の整備が中心でしたが、この制度では接遇や情報発信など、いわゆる“ソフト面”にも注目しています。観光施設の取り組みや姿勢を評価の対象とすることで、ユニバーサルツーリズムの推進や共生社会への理解促進にもつながると期待されています。
“心の”バリアフリーとは?
「心のバリアフリー」とは、段差やトイレ設備などの物理的な障壁を取り除くだけでなく、多様な心身の特性をもつ人々に対して、思いやりや理解をもって接する姿勢のことです。例えば、筆談への対応、ゆっくりとした話し方、気配りのある声かけなども、心のバリアフリーに含まれます。
観光庁が推進する認定制度では、こうした接遇姿勢や情報提供といった“ソフト面”の取り組みも評価の対象となっています。人と人との関係性に注目したこの考え方は、誰もが安心して旅行を楽しめる社会を実現するうえで、重要な要素といえるでしょう。
心のバリアフリー認定制度の対象となる観光施設の種類
心のバリアフリー認定制度では、対象となる観光施設を「宿泊施設」「飲食店」「観光案内所」「博物館」の4つに分類しています。

宿泊施設には、旅館業法の営業許可を受けたホテル・旅館に加え、住宅宿泊事業法に基づく民泊も含まれます。飲食店は、食品衛生法に基づく特定の営業許可を有する店舗が対象です。
観光案内所については、日本政府観光局が認定する施設のほか、同等の機能を担う案内所も含まれます。博物館は、博物館法に基づいて登録された施設や、それに準じた文化施設が該当します。
これらの施設で、バリアフリー設備といったハード面だけでなく、接遇姿勢や情報発信などソフト面での取り組みも評価対象となるのが特徴です。
心のバリアフリー認定制度を受けた施設の主な取り組み内容
心のバリアフリー認定を受けた施設では、利用者一人ひとりへの配慮を重視した「ソフト面での対応」が中心となっています。例えば、車いすや補助器具の貸し出し、筆談・手話による応対、障がい特性に応じた接遇マニュアルの整備などがその一例です。
また、従業員に対しては、年1回以上のバリアフリー研修を実施し、障がいのある方や高齢者への理解を深める取り組みも行われています。さらに、宿泊予約サイトや自治体の観光情報サイトを通じて、施設のバリアフリー対応状況を積極的に発信している点も特徴的です。
心のバリアフリー認定制度を受けるための3つの基準とは
心のバリアフリー認定制度では、施設の対応力を評価するために、ハード面だけでなく「配慮の見える化」が重視されます。ここでは、その具体的な内容について順に解説していきます。
基準①:バリアフリー補完措置を3つ以上実施
心のバリアフリー認定制度では、物理的な設備だけでなく、誰もが安心して施設を利用できる「補完的な配慮」も重視されています。
認定基準の1つである「バリアフリー補完措置」では、段差を解消する可動式スロープの設置、車いすやシャワーチェアの貸し出し、筆談具や手話による対応など、施設内のバリアを補う取り組みを3つ以上実施していることが求められます。

こうした工夫は、障がいのある方や高齢者が快適に施設を利用するための支えとなるだけでなく、すべての来訪者に対するおもてなしの姿勢としても評価されます。
基準②:年1回以上の教育訓練
心のバリアフリー認定制度では、年1回以上の教育訓練の実施が認定基準の1つとされています。目的は、障がいのある方や高齢者への対応力を、職員が継続的に高めていくことにあります。
具体的には、接遇マニュアルを活用した社内研修や、観光庁が提供する研修動画の視聴、外部講師を招いた勉強会などが該当します。また、施設の公式サイトでバリアフリー情報を発信する担当者が、適切な発信方法を学ぶ取り組みも含まれます。

こうした教育訓練を通じて、施設全体の対応品質が底上げされ、利用者にとっての安心感にもつながります。
基準③:自社サイト以外での情報発信
心のバリアフリー認定制度では、自社サイト以外のメディアで情報を発信しているかどうかも、重要な認定基準の1つとされています。

たとえば、宿泊予約サイトやグルメサイト、観光協会の公式ページ、バリアフリー観光ポータルなどに、「車いす対応」「筆談対応可」「刻み食対応」などの情報を掲載しておくことが求められます。こうした情報は、利用者が事前に施設の対応状況を把握するうえでの安心材料となり、旅行先を選ぶ際の大きな判断材料にもなります。
情報を発信する媒体が多いほど、より多くの人に施設の取り組みが伝わりやすくなります。
心のバリアフリー認定制度の申請方法と流れ
心のバリアフリー認定制度を取得するには、所定の手続きと基準に沿った準備が必要です。ここでは、申請に必要な書類と手続き、そして窓口や更新のタイミングについて詳しく見ていきましょう。
申請に必要な書類と手続き
心のバリアフリー認定制度を申請するには、所定の申請書に加え、必要な書類を揃えて提出する必要があります。主な提出書類としては、施設の営業許可証、認定対象施設であることを示す証明書類、認定基準に基づいた取り組み内容を示す写真や資料、研修実績の記録などが挙げられます。
これらの書類を準備したうえで、施設の所在地を管轄する地方運輸局へメールで提出します。申請は通年で受け付けており、不備がなければ原則として35営業日以内に審査が行われます。
書類作成の際は、施設名や所在地が営業許可証の記載と一致しているかを確認し、正確に記載することが大切です。また、バリアフリーの取り組みや研修履歴、自社サイト以外での情報発信内容なども整理しておくと、申請がスムーズに進みます。
申請窓口と更新のタイミング
心のバリアフリー認定制度の有効期間は5年間です。更新を希望する場合は、有効期限の90日前から30日前までに更新申請を行う必要があります。更新時も、初回と同様に取り組み内容や研修記録などの提出が求められるため、日頃からの記録管理が大切です。
申請内容について不明点がある場合は、施設所在地を所管する地方運輸局へお問合せください。一部地域では、伊勢志摩バリアフリーツアーセンターのような地域支援機関が申請手続きの相談を受け付けている場合もあるので、確認してみましょう。
心のバリアフリー認定施設を選ぶメリットと制度の社会的意義
心のバリアフリー認定制度は、利用者に安心感を提供するだけでなく、施設側にも多くのメリットをもたらす制度です。ここでは、利用者・事業者それぞれの視点から制度のメリットを紹介します
利用者にとっての安心材料
認定マークの掲示や情報発信によって、その施設が「心のバリアフリー認定施設」であることがひと目でわかるのは、利用者にとって大きな安心材料になります。
特に、障がいのある方や高齢者にとっては、設備の充実だけでなく、スタッフの対応や施設全体の配慮姿勢が重要な判断基準となります。
認定を受けた施設では、段差の解消や備品の貸し出しといった物理的な対策に加えて、研修を受けたスタッフによる丁寧な接遇や、外部メディアを活用した情報発信が行われています。こうした取り組みにより、「この施設なら安心して利用できる」という信頼感が生まれています。
旅行先を選ぶ際、事前に不安を軽減できる認定制度の存在は、利用者にとって心強い判断材料です。

事業者にとってのメリットも
「心のバリアフリー認定制度」への登録は、利用者の安心につながるだけでなく、事業者側にもさまざまなメリットがあります。
まず、認定マークの取得により、施設の信頼性や社会的配慮を外部に示すことができ、他の施設との差別化につながります。さらに、観光庁のウェブサイトや外部メディアで施設名が紹介されることで、集客力の向上も期待できます。
加えて、今後の補助金申請や国の高付加価値化事業などにおいて、認定が加点要素として評価されるケースもあり、経営面での優位性を得る可能性があります。
また、従業員の教育や接遇の質を見直す機会にもなり、サービス全体の向上にもつながります。結果として、顧客満足度の向上にも貢献するでしょう。
制度を活用した安心・安全なバリアフリー旅行とは?
旅行を計画する際、高齢の家族や障がいのある方と一緒に安心して過ごせるかどうかは、多くの方にとって大きな関心事です。そんなとき頼りになるのが「心のバリアフリー認定制度」。認定施設を選ぶことで、設備だけでなく接遇や情報提供においても配慮が行き届いた旅行が実現します。次に、その具体的な違いや支援サービスについて見ていきましょう。
認定施設を選ぶとどう違う?
「心のバリアフリー認定施設」を選ぶ最大のメリットは、ハード面だけでなく“心の配慮”にも重点を置いたサービスが整っていることです。例えば、車いすや補助具の貸し出し、筆談や手話での対応、障がい特性に応じた接遇マニュアルの整備など、利用者の不安を軽減する工夫が行き届いています。
さらに、公式サイト以外の外部メディアでも施設情報が発信されているため、事前に対応状況を確認できる点も安心材料となります。認定マークが掲示されていればひと目で判断しやすく、旅行先や外出先を選ぶうえで信頼できる指標になります。
バリアフリー旅行を支援するサービスも活用する
バリアフリー旅行を安心かつ快適に楽しむためには、専門の支援サービスを活用するのもおすすめです。
例えば「バリアフリー旅行.com」では、車いす対応の宿泊施設や移動手段、刻み食への対応が可能な食事施設など、障がいのある方や高齢者のニーズに応じた旅行プランを提供しています。さらに、介助者の同行手配や現地でのヘルパー派遣、移動支援なども依頼できます。
情報収集や予約の手間を自力で行うのが難しい場合でも、プロのサポートを受けることで、家族や福祉施設の職員の負担を減らしながら旅行を実現できます。
心のバリアフリー認定制度を理解して、安心できる旅を実現しよう
心のバリアフリー認定制度は、高齢者や障がいのある方が安心して観光を楽しめる社会の実現を目指す取り組みです。制度の概要や認定基準、申請方法を理解することで、施設側はユニバーサル対応の質を高める契機となり、利用者側も安心して選べる施設の選定が可能になります。
また、実際に認定を受けた施設の取り組み事例からは、思いやりと配慮に基づいたサービスの重要性がよくわかります。旅行の計画時には、認定マークの有無やバリアフリー対応情報の発信状況にも目を向け、制度を活用した旅を意識してみましょう。
制度の理解が深まれば、施設選びの視点が広がり、誰にとっても快適で思い出に残る旅行を実現できます。ぜひ本制度を1つの基準として、次の旅先選びに活かしていきましょう。