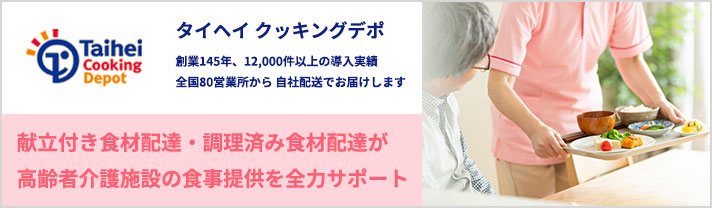- 投稿日 2025/06/13
- 更新日 2025/08/01
バリアフリー法とは?2025年改正の要点・義務・認定制度までわかりやすく解説
障がい者施設様向け
知識

高齢者や障がいのある方も、誰もが安心して移動や施設の利用ができる社会の実現を目指して制定されたのが「バリアフリー法」です。建築物や交通機関などのハード面の整備に加え、近年では「心のバリアフリー」といったソフト面の配慮も重視されています。さらに、2025年には多目的トイレや駐車場などの基準が見直され、対象施設に求められる対応も拡大されつつあります。
そこで今回は、バリアフリー法の基本的な仕組みや対象施設、改正内容まで、実務に役立つ情報をわかりやすく解説します。
目次
バリアフリー法とは?ハード整備と「心のバリアフリー」を両輪で進める法律

バリアフリー法(正式名称:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)は、高齢者や障がいのある方を含むすべての人が、安心して移動・利用できる社会を目指して制定された法律です。
2006年に施行されたこの法律では、建築物や交通機関、道路、公園といったハード面の整備を進めると同時に、「心のバリアフリー」にも重きが置かれています。これは、国民一人ひとりが多様な人々に理解と配慮をもって接することの重要性を示した考え方です。
特に、公共施設や商業施設など一定の規模を超える建物については、段差の解消や多目的トイレ、エレベーターの設置といったバリアフリー対応が義務化されており、施設の種類ごとに基準が設けられています。
さらに、2025年にはトイレや駐車場に関する基準が見直され、より一層の対応が求められるようになりました。
バリアフリー法の歴史と背景|ハートビル法・交通バリアフリー法との違い
現在のバリアフリー法は、建築物や交通機関など多岐にわたる分野の整備を包括的に定めていますが、その背景には段階的な法制度の整備と社会的な要請の積み重ねがありました。ここでは、1994年のハートビル法から2006年の統合までの流れや、制定当時の社会的背景についてみていきましょう。
法制度の変遷
バリアフリー法は、3つの段階を経て整備されてきました。まず1994年に、「ハートビル法(高齢者・身体障害者等が利用しやすい建築物の促進に関する法律)」が制定され、建物におけるバリアフリー化が進められました。
続いて2000年には、駅やバスなどの公共交通機関を対象とした「交通バリアフリー法」が成立します。そして2006年、これまで別々に整備されてきた建築物・交通機関に関する制度を統一・拡充し、包括的に移動等の円滑化を図る法律として、「バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)」が施行されました。
制定の社会的背景
バリアフリー法が制定された背景には、急速な高齢化の進行と、共生社会の実現に向けた社会的要請の高まりがあります。
1990年代以降、日本では高齢者や障がい者の移動・生活を支える制度の整備が求められるようになりました。1994年にはハートビル法、2000年には交通バリアフリー法が制定され、いずれもバリアフリー社会への基礎を築くものとなりました。
これらの法制度を統合し、建築物・交通機関・道路などを包括的に対象としたのが、2006年に施行されたバリアフリー法です。
さらに2010年代には、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を見据え、訪日外国人を含む多様な人々が安心して利用できる施設の整備が重視されました。
2025年改正のバリアフリー基準の主な変更点
2025年6月に施行されたバリアフリー法の改正では、施設の利便性や安全性を一層向上させることを目的に、トイレや駐車場、劇場などの施設に関する具体的な基準が見直されました。ここでは、法改正によって変わった主なポイントをわかりやすく解説します。
多目的トイレの設置義務

2025年6月のバリアフリー法改正により、多目的トイレの設置基準が大きく見直されました。従来は建築物内に1箇所以上の設置が求められていましたが、改正後は原則として「各階に1以上」の設置が義務づけられます。
これにより、車いす使用者や介助が必要な方も、階層に関係なくトイレを利用できる環境整備が求められるようになりました。対象となるのは特別特定建築物で、一定規模以上の新築や改築の際には、バリアフリー基準への適合が義務となります。
今回の改正は、高齢者や障がいのある方の移動に伴う不便を解消し、誰もが使いやすい建築環境の実現を促す重要な一歩といえるでしょう。
駐車場・劇場等の改正

2025年6月に施行されたバリアフリー法の改正により、駐車場や劇場に関する基準も大きく見直されました。
駐車場では、車いす使用者用のスペース設置数が駐車台数に応じて義務付けられます。具体的には、駐車台数が200台以下の場合は2%以上、200台を超える場合は1%に加えて2台以上の確保が必要です。
また、劇場や映画館などの客席にも新たな設置基準が設けられました。座席数が400以下の場合は2席以上、400を超える場合は全体の0.5%以上の車いすスペースを設けることが求められます。
これにより、単なる移動のしやすさだけでなく、「観る・楽しむ」といった体験のバリアも取り除かれ、誰もが文化や娯楽に触れやすい環境が整いつつあります。
バリアフリー法の法的義務とは?
バリアフリー法では、すべての施設に同じ整備義務が課されているわけではありません。ここでは、まず両者の違いと位置づけについて整理し、制度理解を深めていきましょう。
努力義務と義務の違いは?
バリアフリー法では、施設の種類や規模、建築時期に応じて「義務」と「努力義務」が明確に区別されています。
新築や大規模改修を行う場合、一定規模以上の「特別特定建築物」には、バリアフリー基準への適合が義務として課されます。一方、既存の建物や小規模施設などについては、法的強制力のない努力義務として、可能な範囲での対応が求められるにとどまります。
義務に違反した場合は罰則が科される可能性がありますが、努力義務にはそのような罰則はありません。ただし、対応の有無によって、社会的な信頼性や利用者の満足度、自治体の補助金対象かどうかといった点に違いが生じることもあります。
そのため、たとえ努力義務であっても、前向きに取り組む姿勢が重要です。
義務対象となる「特別特定建築物」の種類と条件
バリアフリー法では、高齢者や障がい者を含む多くの人が利用する建築物のうち、一定の条件を満たすものを「特別特定建築物」と定義しています。
対象となるのは、学校・病院・劇場・百貨店・ホテル・官公署・福祉施設など、19類型に分類される施設です。原則として、延べ面積2,000㎡以上(公衆便所は50㎡以上)の新築や大規模改修を行う際には、バリアフリー基準への適合が義務づけられています。
義務の内容には、廊下の幅員確保、段差の解消、エレベーターや多目的トイレの整備などが含まれ、移動しやすい環境を整えるための具体的な基準が定められています。

建築確認時に必要な提出書類と審査の流れ
バリアフリー法に基づき、特別特定建築物を新築・増築・改築する際には、建築物移動等円滑化基準への適合が義務となっています。
そのため、建築確認申請時には通常の申請書類に加え、「バリアフリー法チェックリスト」の提出が求められます。このチェックリストでは、出入口・廊下・トイレ・エレベーターなど、各設備が基準に適合しているかを示し、建築主事または指定確認検査機関による審査を受ける流れです。
提出部数は正副2部が原則となっており、自治体によっては独自の様式が定められていることもあるため、事前に確認しておく必要があります。
なお、申請時点で基準に適合していない場合には、設計変更や追加整備を求められるケースもあります。
バリアフリー法の認定制度とは?
バリアフリー法では、一定の条件を満たす建築物について、国や自治体が認定を行う制度が設けられています。ここでは、認定制度の概要や対象となる建築物の範囲、認定によって得られるメリット、申請の流れについて詳しくみていきましょう。
認定制度の仕組み
バリアフリー法における「認定制度」は、単に基準を満たすだけでなく、より高い水準でのバリアフリー整備を促すための仕組みです。
この制度では、建築物が法定の「建築物移動等円滑化基準」を上回る「誘導基準」に適合している場合、所管の行政庁から「認定建築物」として認定を受けることができます。
認定を受けた建築物には、容積率の緩和や税制上の優遇措置、広報効果といったメリットがあるため、民間施設でも導入が進んでいます。
認定対象となる「特定建築物」の範囲
バリアフリー法における「特定建築物」とは、多くの人が利用する施設であり、認定制度の対象とされる建築物を指します。具体的には、学校、病院、劇場、百貨店、ホテル、共同住宅、事務所、福祉施設、飲食店など、さまざまな用途の建築物が該当します。
これらの建築物が、法定の「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合している場合、所管行政庁から認定を受けることが可能です。認定を受けると、容積率の緩和などの特例措置が適用されるため、民間事業者にとっても導入のメリットは大きいといえます。
バリアフリー法の認定で得られるメリット
バリアフリー法に基づく認定を受けた建築物には、設計面や運営面でさまざまなメリットがあります。例えば、バリアフリー対応のために必要な広い廊下や多目的トイレなどのスペースは、延べ面積の1/10まで容積率から除外できる特例が適用され、設計の自由度が高まります。
また、延べ床面積2,000㎡以上で昇降機を設置している施設では、所得税や法人税において割増償却が認められるなど、税制上の優遇措置も受けられます。そのほかにも、補助金や低利融資制度の活用、認定マークの掲示による利用者の安心感やPR効果など、事業者にとって多くの利点があります。
認定申請の流れ
バリアフリー法における認定申請は、施設が「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合していることを所管行政庁に申請し、認定を受けることで完了します。申請は、原則として建築確認申請と同時に行うことが推奨されており、「認定申請書」「チェックリスト」「設計図書」などを正副2部ずつ提出する必要があります。
手続きの窓口は各自治体が担当しており、事前相談を通じて申請要件や必要書類を確認しておくことが大切です。認定を取得することで、容積率の緩和や税制優遇などの特例措置を活用できるため、設計の初期段階から申請を視野に入れて準備を進めるのが望ましいでしょう。

「心のバリアフリー」とは?ソフト面での配慮も重要に
バリアフリー法では段差の解消やトイレの整備など、建物の構造に関する対策が注目されがちですが、真のバリアフリーを実現するには意識面での配慮も欠かせません。2018年の法改正を機に「心のバリアフリー」という考え方が明確に位置づけられ、国民一人ひとりの理解や協力が重視されるようになりました。ここではその基本概念や、具体的な取り組み事例を紹介します。
心のバリアフリーとは?
「心のバリアフリー」とは、段差の解消や設備の整備といった物理的な対応にとどまらず、誰もが安心して暮らせる社会を実現するための“意識面での配慮”を指します。その考え方の基盤には、障がいの原因を個人の機能に求める「医学モデル」ではなく、社会の側にある障壁に着目する「社会モデル」があります。
平成30年の法改正では、心のバリアフリーの推進が国民の責務として明記され、教育や啓発、合理的配慮の提供がより重視されるようになりました。また、外見ではわかりづらい障がいや体調に対する配慮として「ヘルプマーク」の普及も進められており、これも心のバリアフリーの一例といえます。

自治体・企業の取り組み事例
心のバリアフリーを推進するうえで、自治体や企業による先進的な取り組みが各地で広がっています。
例えば、大阪府では「福祉のまちづくり条例」を制定し、障がい当事者とともに現地で検証を行いながら基準を策定。また、トイレ内に介護ベッドを設置するなど、独自の整備も進められています。
横浜市では、施設ごとに整備マニュアルを作成し、細やかな配慮が行き届いた設計の実現を目指しています。
企業においても、ヘルプマークの導入や、従業員を対象とした障がい理解研修の実施など、ソフト面での取り組みが増えてきました。
旅行者目線でみるバリアフリー法
バリアフリー法は、施設管理者や自治体を対象とした制度という印象をもたれがちですが、旅行者にとっても重要な意味をもつ法律です。
多目的トイレや車いす用の駐車場、段差のない出入口などが整備された施設は、観光や外出時の安心感につながります。特に2025年の法改正では、劇場やホテル、商業施設といった身近な場所での整備基準が強化され、旅行中の移動や施設利用がより快適になることが期待されています。
また、視覚・聴覚への配慮を取り入れた設備や、「心のバリアフリー」に関する取り組みも広がっており、障がいのある方だけでなく、高齢者や小さな子ども連れの方にも利用しやすい環境が整いつつあります。

バリアフリー法を理解して、誰もが安心して移動・利用できる社会をつくろう
バリアフリー法は、高齢者や障がい者をはじめとしたすべての人が、安心して移動し施設を利用できる社会を実現するための重要な法律です。2006年の施行以来、段差の解消やトイレ・駐車場の整備などハード面の基準に加え、「心のバリアフリー」といったソフト面の配慮も進められてきました。
特に2025年の改正では、多目的トイレの各階設置義務や劇場の車いすスペース拡充など、利用者目線の改定が加速しています。施設の種類や規模に応じて「義務」と「努力義務」が区別され、適切な対応が求められます。
施設管理者や自治体職員は、制度の内容を正しく理解し、基準に沿った整備を行うことで、誰もが快適に過ごせる社会づくりに貢献していく必要があります。今こそ、法の理念を実現する一歩を踏み出しましょう。