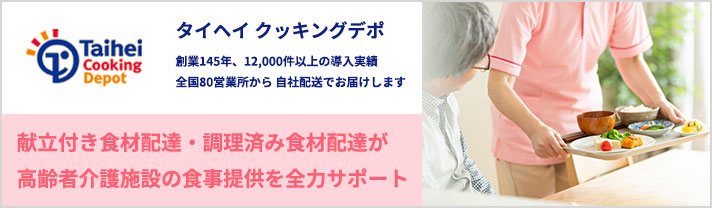- 投稿日 2025/06/16
- 更新日 2025/08/01
バリアフリーの問題点とは?日常生活や社会に残る課題を多面的に解説
障がい者施設様向け
知識

障がいのある方が安心して暮らせる社会の実現には、バリアフリーの理解と実践が欠かせません。しかし実際には、段差や設備の不備といった目に見える障壁だけでなく、制度の不備や情報不足、周囲の無理解といった“見えにくいバリア”が多く存在しています。
そこで今回は、こうした多面的な課題を整理し、支援者が気づき・行動するための視点とヒントを詳しく解説します。
目次
そもそもバリアフリーとは?
バリアフリーとは、年齢や障がいの有無にかかわらず、すべての人が安全で快適に暮らせるよう、生活上の「障壁(バリア)」を取り除く考え方です。
例えば、段差をなくす、手すりを設けるといった物理的な対策だけでなく、情報のわかりやすさや制度の整備、そして人々の意識や配慮といった“心の面”も含まれます。
特に日常生活では、支援者や周囲の人が気づきにくい「見えないバリア」が存在することもあり、注意が必要です。
バリアフリーの主な問題点
バリアフリーの考え方が広まりつつある一方で、現実には多くの課題が残されています。ここでは、バリアフリーの推進を妨げる主な問題点を4つの視点から整理し、それぞれに潜む課題について詳しくみていきます。
物理的バリアの問題

物理的バリアとは、建物や設備の構造に起因する障害を指します。車いす利用者や視覚障がい者にとって、移動や利用を妨げる要因となるものです。
具体例としては、段差や階段、狭い通路、手すりの未設置、エレベーターの不足などが挙げられます。こうしたバリアは住宅だけでなく、駅や商業施設、公共機関など、さまざまな場所に存在しており、日常生活に支障をきたす場面も少なくありません。
また、施設の一部だけがバリアフリー化されているケースもあり、利用者全体の利便性にはつながっていないこともあります。支援者にとっては、外出先や施設内にどのような障害があるかを事前に把握し、適切な対策を講じることが大切です。
物理的バリアの有無は、暮らしの自由度や安心感に大きく影響します。
制度・ルールの未整備
バリアフリーを進めるには、設備の整備だけでなく、制度やルールの整備も欠かせません。
しかし現状では、法律や基準が十分に整っていなかったり、現場にまで浸透していなかったりするため、障がいのある方が不利益を被る場面が少なくありません。例えば、駅においてエレベーターの設置義務がない小規模施設や、合理的配慮の提供が事業者の裁量に委ねられているケースなどは、制度の不備が利用者の行動を制限する要因となっています。
さらに、自治体ごとの対応にばらつきがあるため、住む地域によって支援の質や範囲に差が出てしまうのも大きな課題です。
情報・文化面での障壁

バリアフリーの実現を妨げる要因には、情報や文化の側面に潜む障壁もあります。
例えば、障がいのある方に必要な情報が公開されていても、難解な表現や小さな文字、音声案内の不足などによって、実際には十分に伝わっていないことがあります。施設やサービスの利用方法が不明瞭で、事前に確認できない場合も多く、利用を断念せざるを得ないケースも少なくありません。
また、「障がい者=特別な存在」といった先入観や、「配慮がかえって迷惑になるのでは」といった遠慮の気持ちも、文化的なバリアとなって立ちはだかります。
心のバリア・無理解
物理的な設備が整っていても、周囲の無理解や思い込みが、障がいのある方の行動や気持ちを制限してしまうことがあります。例えば、「支援は特別な人が行うもの」「声をかけるのは失礼かもしれない」といった先入観が、支援のきっかけを遠ざけてしまうこともあります。
こうした“心のバリア”は目に見えにくく、善意のつもりの言動が、知らず知らずのうちに孤立を生む原因となることもあります。また、障がいの特性についての理解が不十分なことで、不適切な対応や誤解を招いてしまうケースも少なくありません。
支援者としては、「わからない」ことを恐れず、学び続ける姿勢が求められます。
生活の中にある具体的なバリアの実例
日常生活の中には、障がいのある方にとって見えにくいバリアが数多く存在します。ここでは、具体的な生活シーンごとに残されたバリアの実例を取り上げ、その課題と改善の視点について考えていきます。
家庭や住宅に残るバリア

家庭や住宅の中にも、見過ごされがちなバリアが多く残されています。例えば、玄関や室内に段差があると、車いすを使用する方や足元の不安定な高齢者にとって、大きな負担になります。
また、開き戸の使用や狭い廊下は、移動の自由を妨げる原因となりがちです。トイレや浴室のスペースが十分でなかったり、手すりが設置されていなかったりすると、介助が難しくなるうえ、転倒などのリスクも高まります。
さらに、照明の明るさやスイッチの位置、家具の配置といった細かな要素も、安全性や快適性に大きく影響します。毎日使う空間だからこそ、支援者自身が「当たり前」と感じている点に改めて目を向けることが重要です。
交通機関や公共施設のバリア
駅やバス停、公共施設など、外出時に利用する場所にも、さまざまなバリアが残されています。例えば、エレベーターやスロープが設置されておらず、階段のみでの移動を強いられる駅では、車いす利用者や高齢者の移動が大きく制限されてしまいます。
バスを利用する際も、低床車が常時運行していない地域では、乗降時に支援を必要とするケースが多く見られます。さらに、案内表示が視覚または聴覚のどちらかに偏っていたり、情報提供が一方向のみであったりすると、必要な情報にアクセスできないこともあります。
公共施設においては、多目的トイレの数が不足していたり、職員による対応マニュアルが整っていない場合もあり、安心して利用できる環境とは言いにくいこともあります。
こうした状況に対し、支援者は事前の下見や情報収集を行い、利用者の立場に立って環境のバリアに気づくことが大切です。
医療・教育現場におけるバリア

医療機関や学校といった公共性の高い現場にも、障がいのある方にとって見過ごせないバリアが残されています。
例えば病院では、診察室や検査室までの移動経路に段差や狭い通路がある、案内表示が視覚や聴覚への配慮に欠けているといった課題が見られます。さらに、障がいの特性に応じた診療体制が整っておらず、意思疎通や診察対応が難しいケースも少なくありません。
教育現場においても、教室内のレイアウトや教材の形式、支援体制に差があることで、学習機会の平等が確保されにくい状況が見受けられます。また、教員や医療スタッフの理解不足により、不適切な対応が行われてしまうこともあります。
支援者としては、現場の物理的な環境だけでなく、人的な理解や連携の不足にも目を向けることが重要です。
バリアフリー化が進まない理由とは?
バリアフリーの必要性が広く認識されるようになった一方で、社会全体での実現には依然として多くの壁があります。ここでは、バリアフリー化が進みにくい主な理由を整理し、解説していきます。
制度はあっても実行力が伴っていない
バリアフリーに関する法制度は一定程度整備されているものの、現場では十分に実行されていないのが実情です。例えば、バリアフリー法の義務が一部の施設に限定されていたり、対応が事業者の自主判断に委ねられていたりするため、取り組みには地域や施設ごとに差が生じています。
さらに、制度が存在していても、現場の理解不足や予算・人材の制約によって、具体的な施策が進まないケースも見受けられます。こうした状況では、制度の有無にとどまらず、実際の運用や効果に目を向ける視点が欠かせません。
費用・人材・スペースの制約が大きい
バリアフリー化を進める際に立ちはだかる大きな課題には、費用・人材・スペースの確保もあります。
例えば、スロープやエレベーターの設置、段差の解消といった工事には多くの資金が必要となり、特に中小規模の施設では大きな負担と感じられがちです。また、設備が整っていても、介助や案内に対応できる職員が不足していることで、現場の運用が追いつかないこともあります。
さらに、建物の構造上スペースを確保できず、改修自体が難しいケースも少なくありません。このように、物理的・人的な制約が重なることで、理想とするバリアフリー環境の実現が後回しにされてしまう現状があります。
支援者としては、「できない理由」にとらわれるのではなく、「どうすれば実現できるか」を考える姿勢が大切です。
「健常者基準」のまま設計されている

多くの建物やサービスは、いまだに「健常者を基準」とした設計や運用が前提となっており、これもバリアフリー化を妨げる要因の1つとなっています。
例えば、階段のある出入口や、視覚情報に依存した案内表示は、障がいのある方にとって利用しづらい構造です。設計段階で当事者の視点が反映されていないことで、後から不便が判明しても抜本的な改善が難しい場合もあります。
また、「一部に対応していれば十分」と判断されるケースも少なくなく、結果として施設全体の使いやすさにはつながっていないのが現状です。
支援者は、見た目にわかる設備だけで満足せず、「誰もが使いやすいかどうか」という視点で環境を見直す姿勢が求められます。
当事者の声が反映されにくい
バリアフリー施策を進めるうえで重要なのは、実際に障がいのある方の声を反映することです。しかし現実には、その機会が限られていることが少なくありません。
施設や制度が「つくる側の視点」で設計され、「使う側」のニーズが十分に取り入れられていないケースが多く見受けられます。例えば、見た目にはバリアフリー対応されているように見えても、実際には使い勝手が悪く、かえって不便を感じることもあります。
また、意見を表明する場が設けられていても、当事者が発言しにくい雰囲気や仕組みが障壁となり、参加が難しい状況もあります。
支援者としては、日常的な対話やアンケートを通じて声を丁寧に拾い上げ、施設や制度づくりに反映していく姿勢が大切です。
情報の不足と周知の遅れ
バリアフリー施策や設備が整っていても、その情報が十分に届かなければ、実際の利用には結びつきません。例えば、バリアフリールートや多目的トイレの設置場所、各種支援制度の内容などがわかりにくく、検索しても最新の情報が得られないという声は少なくありません。
また、情報が更新されていなかったり、視覚や聴覚に配慮のない形式で発信されていたりすることも、利用を妨げる一因となります。制度改正や新たな取り組みについても、現場に伝わるまでに時間がかかり、その間に支援を受けられず困難を抱えるケースも見られます。
支援者としては、信頼できる情報源を日ごろから把握し、当事者にとって必要な情報をわかりやすく、タイムリーに届ける姿勢が欠かせません。
バリアフリー社会の実現に向けた解決策
バリアフリーの重要性が広く認識される一方で、制度の不備や設備不足、心の無理解など、現場では依然多くの課題が残されています。ここでは、多様な立場の声を反映する仕組みづくりや情報発信の工夫、心のバリアフリー教育など、具体的な解決策をわかりやすく紹介します。
多様な立場からの声を反映する仕組みづくり

多様な立場の声を反映するには、制度や設備を「利用する人」の視点で見直すことが欠かせません。障がいのある方やその家族、支援者、教育・医療関係者など、実際の暮らしにかかわる人々の意見を制度設計やまちづくりに活かす仕組みが求められています。
例えば、意見交換の場を設ける、定期的なアンケートを実施する、施設利用者のフィードバックを制度に反映するなどの工夫が挙げられます。
さらに、多様なニーズに気づくためには、当事者や支援者だけでなく、行政・企業・設計者など、さまざまな立場が連携・協働することも重要です。一方向的に「提供する」だけでなく、共に考え、共につくり上げるという姿勢こそが、誰もが安心して暮らせる社会を支える土台になります。
「気づく力」を育てる心のバリアフリー教育
バリアフリー社会の実現には、設備や制度の整備だけでなく、一人ひとりが「気づく力」を育むことが重要です。
例えば、学校教育や地域活動の中で、障がいのある方の視点を学ぶ機会を設けることで、心のバリアに気づくきっかけが生まれます。「困っている人に気づく」「自分にできることを考える」といった日常的な意識が、支援の第一歩につながります。
また、体験学習やロールプレイ、当事者の話を聞く授業などは、共感力を育てる手段として有効です。こうした取り組みを、支援者や教育関係者が意識的に導入することで、子どもから大人まで共生社会の担い手を育てることができます。
「見えないバリア」に気づける人が増えることで、社会の在り方も少しずつ変わっていきます。
情報の見える化と発信の充実

バリアフリーを推進するうえでは、必要な情報が誰にとっても「見える形」で届くことが大切です。
例えば、バリアフリールートや多目的トイレの設置場所、支援制度の内容などが、施設案内やWebサイト上でわかりやすく示されているかは、利用者の安心感に直結します。文字情報だけでなく、図解や写真、音声ガイド、多言語対応といった工夫によって、情報の伝わり方は大きく変わります。
さらに、利用者の声を反映しながら情報の質を見直し、更新頻度を保つことで、信頼性の向上にもつながります。
加えて、行政や施設側からの一方的な発信だけでなく、SNSや口コミ、地域の掲示板などを通じて、情報が多様なルートで共有されることも重要です。こうした広がりが、利用者にとっての判断材料となり、行動を後押しします。
支援者は「知っていて当然」という前提を手放し、情報がどのように届き、どう伝わるかを常に意識することが求められます。
地域・企業・行政の連携による取り組み強化
バリアフリー社会を実現するには、地域・企業・行政がそれぞれの強みを活かしながら、連携して取り組むことが欠かせません。例えば、地域の実情をよく知る自治体、技術や資源を持つ企業、そして現場で支援を行う福祉施設や学校が協力することで、実効性の高い施策が生まれます。
公共施設や商業施設のバリアフリー化においても、行政が補助制度を整備し、企業が技術支援を行い、地域住民の声を反映する場を設けることで、多様なニーズに対応した環境づくりが可能になります。
さらに、防災対策や移動支援、イベント開催時のサポートといった日常のさまざまな場面でも、こうした協働の力が発揮されます。
一人ひとりの意識が社会を変える出発点に

バリアフリー社会の実現には、制度や設備の整備に加えて、一人ひとりの意識と行動の変化が欠かせません。例えば、外出先で困っている人に声をかける、施設の不備に気づいたら改善を提案するといった、日常の小さな気づきが誰かの安心や安全につながります。
支援者や家族、教育・福祉関係者だけでなく、地域に暮らすすべての人が「自分にもできることがある」と意識することが大切です。障がいのある方を特別な存在ととらえるのではなく、共に暮らす一員として自然に受け入れる姿勢が、心のバリアを取り除く第一歩になります。
社会の価値観や文化は、一人ひとりの行動の積み重ねによって育まれていくものです。
誰もが暮らしやすい社会を目指して、今できることから始めよう
バリアフリー社会の実現には、大がかりな制度改革や設備投資だけでなく、日常の中の小さな気づきや行動が欠かせません。誰かが困っていたら声をかける、施設の不備に気づいたら伝えるといった一歩が、障がいのある方の安心や自立につながります。
また、支援者自身が情報の見え方や制度の背景を理解し、当事者の声に耳を傾けることで、より実効性のある支援が可能になります。地域や学校、福祉施設など、それぞれの場でできることを見つけ、少しずつ積み重ねていくことが大切です。
私たち一人ひとりが「共に暮らす社会」を意識して行動することで、未来のバリアフリーは着実に形になっていきます。まずは身近なところから、できることを始めてみましょう。