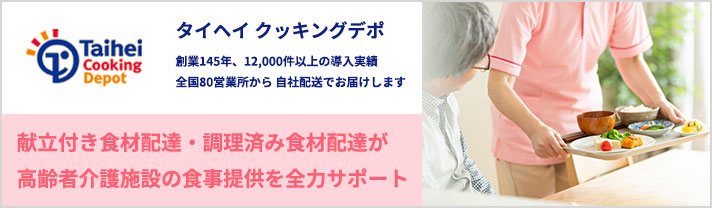- 投稿日 2025/06/20
- 更新日 2025/09/09
SDGsとバリアフリーの関係とは?目標番号・事例・企業の取り組みをわかりやすく解説
障がい者施設様向け
知識

SDGs(持続可能な開発目標)が掲げる「誰一人取り残さない社会」の実現には、障がいの有無や年齢、国籍を問わず、すべての人が安心して暮らせる環境づくり=バリアフリーの推進が欠かせません。
しかし、SDGsとバリアフリーの関係性や、具体的にどの目標に該当するのかを正しく理解している人はまだ多くありません。
そこで今回は、バリアフリーがSDGsとどう結びついているのかをはじめ、4つのバリアの種類や国内外の実践事例、企業や自治体の先進的な取り組みをわかりやすく紹介します。
自社・地域での施策や教育現場での活用のヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
目次
SDGsでバリアフリーが重要視される理由とは?
SDGsがバリアフリーを重視する背景には、「誰一人取り残さない」という基本理念があります。
社会には、障がいや高齢、言語の違いなど、さまざまな事情を抱える人々が暮らしており、そうした人たちが自由に移動し、情報にアクセスし、社会活動に参加できる環境の整備が必要とされています。
バリアフリーの取り組みは、インフラの整備だけでなく、制度の見直しや情報提供、意識の変革にまで広がりを見せています。
これにより、すべての人が平等に暮らせる持続可能な社会の実現が目指されているのです。
また、バリアフリーはSDGsの複数の目標とも深く関わっており、特定の層に限らず社会全体の利便性と包摂性を高める要素として注目されています。
こうした観点からも、バリアフリーはSDGs達成に向けた重要な柱と位置づけられます。
バリアフリーが該当するSDGs目標はどれ?

バリアフリーに関する取り組みは、SDGsの中でも特に「目標10:人や国の不平等をなくそう」と深い関わりがあります。
この目標では、すべての人が社会に参加できる環境の整備が重視されており、障がいの有無に関わらず、移動や生活における障壁の解消が求められています。
あわせて「目標11:住み続けられるまちづくりを」では、交通機関や建築物、インフラの整備を通じた包摂的な都市づくりが掲げられており、バリアフリーの実現がその中核を担っています。
さらに、「目標4:質の高い教育をみんなに」や「目標3:すべての人に健康と福祉を」といった目標とも関連が深く、教育機関や医療施設におけるアクセシビリティの確保も重要な課題です。
バリアフリーの4つの種類とは
バリアフリーという言葉は広く知られていますが、その内容は空間の整備にとどまりません。
ここでは、4種類のバリアの具体例を挙げながら、その特徴や解消への取り組みを紹介していきます。
物理的バリアは空間や設備の障害を指す

物理的バリアとは、建物や公共施設、交通機関などにおける空間的・構造的な障害を指します。例えば、段差のある出入口や幅の狭い通路、エレベーターの設置されていない施設、点字ブロックの未整備といったケースが典型的です。
車いすの利用者や視覚・聴覚に障がいのある人にとって、こうした障壁は日常生活や移動の妨げとなり、社会参加の機会を狭める要因になりかねません。
このようなバリアを解消するには、スロープや自動ドア、音声案内の導入、広いトイレの整備など、具体的な環境づくりが欠かせません。
また、建築や都市計画の段階からユニバーサルデザインの考え方を取り入れることで、誰もが使いやすい空間の実現が可能となります。
制度的バリアは仕組みや法律が障害になるもの
制度的バリアとは、法律や制度、あるいは社会の仕組みが障害となり、本来平等であるべき社会参加が妨げられている状態を指します。
例えば、障がい者の移動を支援するための公共交通機関において、割引制度が十分に整備されていないケースや、合理的配慮が義務化されていない採用制度などがその一例です。
そのほかにも、支援機器の給付対象が限定されている場合や、教育制度の中に個別ニーズに対応できないカリキュラムが残っていることも、制度的バリアといえるでしょう。
こうした制度や仕組みは、意図せずして特定の人々を排除する要因となり、結果的に社会全体の包括性を損なうおそれがあります。
制度的バリアの解消には、法制度や行政サービスの見直しが不可欠です。
そして、多様な立場に立った制度設計を行うことが、バリアフリー社会の実現に向けた前進となります。
情報バリアは情報へのアクセス格差によって生じる

情報バリアとは、障がいの有無や年齢、言語、ITリテラシーの差などによって、必要な情報に平等にアクセスできない状態を指します。
例えば、視覚や聴覚に障がいがある人が文字や音声による情報を十分に得られないケースや、外国語に対応していない行政情報、高齢者がデジタル機器の操作に不安を感じる場面などが該当します。
このような情報格差は、日常生活に支障をきたすだけでなく、社会参加の機会を奪う大きな要因にもなり得ます。
情報バリアを解消するためには、点字や音声案内、やさしい日本語、多言語対応、ウェブアクセシビリティといった複数の手段を組み合わせた情報発信が不可欠です。
意識上のバリアは無理解や偏見から生まれる障壁
無理解や偏見によって生じる「意識上のバリア」は、バリアフリーの推進において大きな障壁となります。
たとえ段差の解消や情報保障が進んでいても、「支援の対象」として障がいのある人を一方的にとらえる意識が残っていれば、真の共生社会は実現しません。
例えば、障がいのある人に対する過度な遠慮や、「健常者とは異なる存在」といった先入観は、無意識のうちに人と人との間に見えない壁をつくります。
このような意識の偏りは、教育の場や職場環境、行政サービスなど、あらゆる場面において不平等を引き起こす原因にもなります。
そのため、制度や設備の整備とあわせて、意識面における改善も欠かせません。
「心のバリアフリー」の考え方と推進のポイント
バリアフリーの実現には、物理的な整備や制度改革だけでなく、私たち一人ひとりの意識の変化も欠かせません。
ここでは、その考え方とSDGsとの関連、推進のための具体的なポイントについて解説します。
「心のバリア」とは?
「心のバリア」とは、障がいのある人や高齢者、外国人などに対して、無意識に抱いてしまう偏見や思い込み、距離感のことを指します。
例えば、「どう接すればよいかわからない」「特別な支援が必要だろう」といった思い込みが、知らず知らずのうちに心理的な壁を生み、相手との間に隔たりを生じさせることがあります。
こうした反応は、悪意や差別の意識からくるものではなく、多くの場合、知識や経験の不足に起因します。
そのため、心のバリアは誰の中にも存在し得るものであり、日常的な気づきや学びを通じて取り除いていく姿勢が求められます。
真のバリアフリーを実現するには、物理的・制度的な整備だけでなく、人の心にある無意識の壁にも向き合う必要があります。
SDGsと心のバリアフリーの関連性
SDGsが掲げる「誰一人取り残さない社会」の実現には、物理的なバリアだけでなく、心のバリアにも目を向けることが欠かせません。
特に目標10「人や国の不平等をなくそう」や目標16「平和と公正をすべての人に」は、差別や偏見の解消を重視しており、心のバリアフリーと深く関係しています。
他者への無理解や無関心は、障がいや多様性への配慮を妨げる原因となるため、意識を変えていくことが共生社会の実現には必要です。
心のバリアをなくすための取り組みは、教育、企業活動、地域づくりなど、さまざまな場面でSDGsの理念と結びつきながら進められます。
心のバリアをなくすには?
心のバリアをなくすには、まず多様な人々と接する機会を意識的に増やし、相互理解を深めることが重要です。
障がいや国籍、年齢などの違いに対して抱く先入観は、直接的な交流や学びを通じて徐々に変化していきます。
また、学校教育や企業研修の場において、共生社会やダイバーシティの視点を取り入れたプログラムを実施することも効果的です。
さらに、当事者の声に耳を傾ける姿勢や、偏見に気づくきっかけとなる情報発信の取り組みも欠かせません。
誰もが無意識に抱いている「普通」という枠組みを見直し、多様性を前提とした価値観を育むことが、心のバリアを減らす第一歩となります。
身近にあるバリアフリーの事例
バリアフリーの取り組みは、特別な施設だけでなく、日常生活のさまざまな場面で実現されています。
ここでは、そうした身近なバリアフリーの実例を紹介し、持続可能な社会に向けたヒントを探っていきます。
公共交通機関で実現されているバリアフリー整備

公共交通機関では、すべての人が安全かつ円滑に移動できるよう、バリアフリー整備が着実に進められています。
駅構内には、エレベーターやスロープ、多機能トイレの設置が広がっており、車いす利用者やベビーカーを使用する人にも配慮した設計が増えています。
さらに、視覚障がい者向けの点字ブロックや音声案内、聴覚障がい者に対応した視覚的な情報表示も充実しつつあります。
バスや鉄道の乗降時には、ノンステップバスの導入や駅員によるサポート体制が整備され、移動のしやすさが高まっています。
これらの取り組みは、物理的な利便性を高めるだけでなく、社会全体の意識変容を促す契機にもなります。
住宅や建物内でのバリアフリー設備

住宅や建物内におけるバリアフリー設備は、高齢者や障がいのある人を含め、誰もが安全かつ快適に暮らせる環境を整えるうえでの基本的な取り組みといえます。
具体例としては、段差を解消するスロープの設置や、広めに設計された廊下やドア、手すり付きの階段やトイレ、滑りにくい床材を使った浴室などが挙げられます。
さらに、視覚障がい者への配慮として、床の色分けや点字案内を取り入れる事例も増加傾向にあります。
これらの設備は特定の人のためだけではなく、けがをしている人や子育て中の家庭など、さまざまな状況において広く役立つものです。
また、新築時だけでなくリフォームの段階でも導入が可能であるため、持続可能な住環境の整備としても効果的といえるでしょう。
街中にあるユニバーサルデザインの実例

ユニバーサルデザインとは、年齢や障がいの有無に関わらず、すべての人が利用しやすいように設計された仕組みや製品を指します。
街中では、視覚障がい者向けの点字ブロックや音声付き信号機、車いすでも安心して通行できるスロープ付きの歩道などが代表例として挙げられます。
さらに、駅構内のピクトグラム表示や多言語対応の案内板も、情報バリアを軽減する工夫として注目されています。
加えて、商業施設におけるオストメイト対応トイレや、段差のない自動ドアなども、多くの人にとって利便性を高める要素となっています。
これらの取り組みは、誰もが安心して移動し、施設を利用できる環境づくりに貢献しています。
企業や自治体によるバリアフリー推進の取り組み
バリアフリーの実現には、企業と自治体それぞれの立場からの取り組みが不可欠です。
ここでは、民間と行政による具体的な推進事例を通じて、現場での実践方法や工夫を紹介します。
民間企業によるバリアフリー推進の事例

民間企業におけるバリアフリー推進の取り組みは、多様な顧客や従業員が活躍できる環境づくりとして各業界で広がりを見せています。
例えば、大手の流通業では、車いす利用者に対応したレジの設置や点字付きサインの導入、店内の段差解消といった具体的な施策が進められています。
IT企業では、視覚や聴覚に障がいのある社員を支援する業務ツールを整備し、誰もが働きやすい職場環境の構築に取り組んでいます。
また、住宅関連企業ではユニバーサルデザイン住宅の開発を進め、展示場で利用体験の機会を提供しています。
このように、企業の業種や業態に応じたバリアフリー施策は、SDGsの目標達成に向けた社会的責任の一環としても注目されています。
自治体が推進するバリアフリーまちづくり施策
自治体では、地域の実情に即したバリアフリー施策を、各種条例に基づいて積極的に展開しています。
多くの自治体は「バリアフリー法第14条」に則り、公共施設や店舗、住宅などの建築物に対して、義務化の対象となる用途の追加や規模の基準緩和を行っています。
例えば、東京都では小規模な物販店や共同住宅にも適用範囲を広げており、大阪府では延べ面積200㎡以上の飲食店に対してバリアフリー対応を義務づけるなど、具体的な整備が進んでいます。
さらに、神奈川県や鳥取県などでは、建築計画に際して福祉団体や当事者の意見を反映する制度を導入しており、より実効性の高い施策として注目されています。
こうした条例や制度の活用を通じて、誰もが安心して暮らせるまちづくりが各地で着実に進められているのです。
観光地や地域インフラにおける整備施策の実例
観光地や地域インフラにおいても、バリアフリー整備は積極的に進められています。
近年では、観光庁が創設した「観光施設における心のバリアフリー認定制度」が注目されており、宿泊施設や飲食店、観光案内所、博物館などがその対象となっています。
この制度では、段差の解消や補助機器の設置、従業員への研修、情報発信など、一定の基準を満たした施設を認定し、誰もが安心して利用できる環境づくりを後押ししています。
さらに、地方自治体との連携によって、駅やバスターミナルなどの交通拠点においても、多言語表示や誘導設備の整備が進行中です。
科学技術の活用による先進的なバリアフリー事例(STI for SDGs)
科学技術を活用したバリアフリーの取り組みは、「STI for SDGs(科学技術イノベーションによるSDGs達成)」の一環として、さまざまな分野で展開されています。
例えば、東京藝術大学では、障がいの有無に関わらず誰でも簡単に演奏できる「だれでもピアノ®」を開発し、音楽を楽しめる環境づくりに貢献しています。
弘前大学では、ビッグデータと先端医療技術を活用し、高齢者の健康と長寿を支える地域づくりを推進しています。
さらに、災害時の避難支援においては、対象者に対してピンポイントで行動を促すアラートシステムの研究が進行中です。
バリアフリーを進めるうえでの課題と対策
バリアフリーを推進するには、物理的な整備だけでなく、制度や意識の面でもさまざまな課題に対応する必要があります。
ここでは、バリアフリーの実現を阻む代表的な課題と、それに対する取り組みの方向性について紹介します。
意識のバリアと心のバリアフリーの重要性
バリアフリーを推進するうえでは、物理的な設備整備や制度の見直しだけでは不十分です。多様な人々が共に暮らす社会を実現するためには、「意識のバリア」にも向き合う必要があります。無意識に抱いてしまう先入観や思い込みは、当事者を傷つけるだけでなく、人間関係を分断させる原因にもなり得ます。
こうした意識の壁を取り除くためには、心のバリアフリーに配慮した教育や、対話の場を設けることが欠かせません。知識の共有や当事者の声に触れる機会を通じて、多様性に対する理解と共感を深めていくことが求められます。
物理的な環境整備と並行して、意識の変化を促す取り組みを進めることが、誰もが尊重される社会づくりのカギとなります。
制度的バリアの存在と法制度の見直し
バリアフリーを推進するうえで、制度的なバリアの存在は軽視できません。
例えば、障がい者の雇用や教育の現場において、制度が現状に合わないまま放置されていると、支援の仕組みが行き届かず、結果的に差別的な扱いが続いてしまいます。
また、法律や行政手続きの設計が特定の人々の利用を前提としている場合、それ自体が新たなアクセス障壁となる可能性もあります。
こうした問題を解消するには、法制度を定期的に見直し、多様な立場の人々の声を反映させることが欠かせません。
バリアフリー施策の実効性を高めるためには、制度そのものが包括的かつ柔軟である必要があります。
公平な社会を築くには、制度面からも積極的にバリア解消に取り組む姿勢が求められます。
物理的バリアへの対策と改善策
物理的バリアへの対策としては、段差の解消やスロープの設置、エレベーターの増設といった空間の整備が欠かせません。
これにより、車いす利用者や高齢者だけでなく、ベビーカーを使用する人や一時的にけがをしている人も、安心して移動できるようになります。
さらに、点字ブロックや手すり、視認性に優れた案内表示の導入も、移動の安全性を高めるうえで効果的です。
新築時だけでなく、既存施設の改修や日常的なメンテナンスも重要な視点といえるでしょう。
自治体や企業には、ユニバーサルデザインの視点を取り入れた環境づくりが求められます。
その際には、専門家や当事者の声を取り入れながら改善を重ねていくことが大切です。
SDGsの目標達成には誰も取り残さないバリアフリー社会の実現が不可欠

SDGsの理念である「誰一人取り残さない社会」の実現には、バリアフリーの推進が不可欠です。
バリアフリーとは、物理的・制度的な障壁だけでなく、情報格差や無意識の偏見といった「心のバリア」まで含めて解消を目指す包括的な取り組みです。
SDGsの目標10「人や国の不平等をなくそう」や目標11「住み続けられるまちづくりを」をはじめ、複数の目標と深く関わりながら、持続可能で包摂的な社会づくりの基盤となっています。
企業・自治体・教育現場など、あらゆる場面での具体的な行動が求められており、今後ますます多様性への配慮が重視されるでしょう。
私たち一人ひとりが障壁に気づき、行動を変えていくことで、誰もが生きやすい未来を共に築いていきましょう。