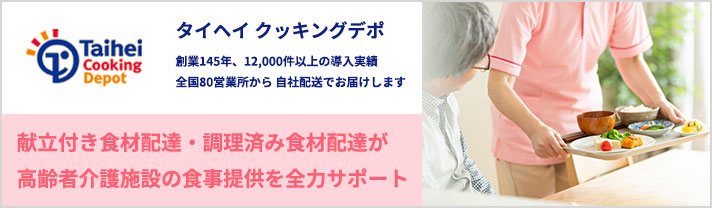- 投稿日 2025/06/21
- 更新日 2025/09/09
車いすでタクシーを利用するには?一般・介護・UDタクシーの違いと選び方を解説
個人旅行向け
障がい者施設様向け
高齢者施設様向け
付き添い
知識

車いすを利用している方やそのご家族にとって、通院や買い物など日常の移動手段の確保は大きな課題です。
特にタクシーの利用を検討する際、「どのサービスを選べばよいのか」「車いすのまま乗れるのか」「介助は受けられるのか」など、疑問や不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、一般タクシー・UDタクシー・介護タクシーの違いや、それぞれの特徴、予約方法、費用の目安、保険の適用条件などをわかりやすく解説しています。
利用目的や身体状況にあわせた最適な移動手段を見つけるヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
目次
車いすでタクシーは利用できる?
車いすを使っている場合でも、状況に応じてタクシーを利用することは可能です。
ただし、乗車方法や対応できる車両には違いがあり、事前の確認が欠かせません。
ここでは、車いす利用者がタクシーを安心して活用するための基本的な情報を紹介します。
車いすで一般タクシーに乗れるケース

一般的なタクシーでも、車いす利用者が乗車できる場合があります。
ただし、対応可能かどうかは「車いすの種類」や「乗客の移乗の可否」によって異なります。
例えば、折りたたみ式の軽量タイプであればトランクや後部座席に収納できるため、乗客が自力で座席へ移動できる場合には問題なく利用できるでしょう。
一方で、電動車いすやリクライニング機能付きの大型タイプは収納が困難であり、一般タクシーでは対応できないケースが多く見受けられます。
さらに、ドライバーによっては介助に対応していないこともあるため、あらかじめ電話で状況を伝えておくと安心です。
通院や短距離の移動などでは、介助者と同乗することで利用しやすくなることもあるため、自身の状況に応じて一般タクシーの活用も検討してみてください。
車いすのまま乗車できるタクシーの種類
車いすに乗ったままでもスムーズに利用できるタクシーとしては、「UD(ユニバーサルデザイン)タクシー」と「福祉・介護タクシー」があります。
UDタクシーはミニバン型の車両が多く、スロープや電動リフトを備えているため、乗降が比較的容易です。
都市部を中心に一般のタクシー会社が導入しており、予約なしで乗車できる場合も見られます。
一方、福祉・介護タクシーは介助を必要とする方のために設計されており、ストレッチャー対応や同乗者用の座席が設けられていることもあります。
こちらは原則として予約制で、介助資格を持つドライバーが乗務します。
利用者の身体状況や目的に応じて、無理のない選択ができるよう、それぞれの特性を確認しておくと安心です。

利用目的に応じたタクシーの選び方
車いすでタクシーを利用する際は、目的に応じたサービスを選ぶことが重要です。
例えば、通院や介護を伴う移動には、乗降時の介助や病院内の付き添いに対応できる介護タクシーが適しています。
反対に、近所への買い物や短時間の外出であれば、車いすのまま乗車できるユニバーサルデザイン(UD)タクシーが便利です。
利用者が自身で座席に移れる場合には、一般タクシーを選択できることもあります。
どのタクシーが適しているかは、体調や移動の目的、必要なサポートの内容によって異なります。
事前に目的を整理し、求める支援内容を明確にしたうえで、最適なサービスを選びましょう。
利用前に確認すべき条件
車いすでタクシーを利用する際には、事前にいくつかの条件を確認しておく必要があります。
まずは、希望するタクシーが車いす対応の車両かどうかを把握することが大切です。
一般タクシーの場合、折りたたみ式の車いすに限って対応しているケースが多く、乗ったままの乗車を希望する場合は、UDタクシーや介護タクシーの予約が求められます。
また、乗降時にサポートが必要な方は、介助可能な乗務員がいるかどうか、介助サービスの有無を確認しておくと安心です。
さらに、地域によっては福祉タクシー券の利用条件や介護保険の適用範囲が異なるため、自治体や運行事業者への確認も欠かせません。
円滑な利用のためには、予約時に車いすの使用や介助の必要性をきちんと伝えておくことが大切です。
一般タクシーと介護タクシーの違いとは?
車いすで外出する際、一般タクシーと介護タクシーのどちらを利用すればよいか迷うことがあります。
ここでは、主な違いと確認すべきポイントを詳しく解説します。
利用対象者と利用条件の違い
一般タクシーは、誰でも利用できる公共の移動手段として運行されており、特別な申請や条件は必要ありません。
一方、介護タクシーは身体に不自由がある方や要介護認定を受けた高齢者など、一定の条件を満たした方が対象となります。
例えば、介護保険の適用を受けるには、要支援や要介護の認定に加え、通院や生活支援といった明確な目的が求められます。
また、事業者によっては利用登録や事前相談が必要な場合もあります。
スムーズに利用するためには、自身が対象に該当するかどうかを確認し、必要な手続きを事前に把握しておくことが重要です。
タクシーの種類ごとに異なる条件を理解したうえで、状況に合ったサービスを選びましょう。
車両設備と乗車方式の違い
一般タクシーと介護タクシーでは、車両の設備や乗車方法に明確な違いがあります。
一般タクシーはセダン型やミニバン型の車両が中心で、乗降口も一般利用者向けに設計されているため、車いす利用者は自力で座席に移るか、介助者の補助を受ける必要があります。
一方、介護タクシーではスロープやリフト、固定用ベルトなどを備えた福祉車両を使用しており、車いすやストレッチャーのまま安全に乗車できます。
また、ステップの高さやドアの幅も広く設計されているため、移動に不安がある方でも安心して利用できます。
身体状況や移動時の負担に応じて適切な車両を選べるよう、設備面の違いを把握しておくことが大切です。
料金体系とドライバーの対応力の違い
一般タクシーの料金は、距離や時間に応じたメーター制が基本であり、特別な事情がない限り追加料金はかかりません。
一方、介護タクシーでは走行距離に加え、乗降や介助にかかる内容や時間によって別途料金が加算される場合があります。
必要となる介助の種類によって費用が変動するため、事前に見積もりを確認しておくと安心です。
さらに、ドライバーの対応力にも違いが見られます。
一般タクシーでは介護資格を持たない運転手がほとんどですが、介護タクシーではホームヘルパーなどの有資格者が対応することもあります。
乗車中の体調変化や安全面への配慮を重視する場合には、専門知識を備えたドライバーが在籍する事業者を選ぶとより安心です。
介護保険が使える「介護タクシー」の条件と申請方法
介護保険を活用することで、介護タクシーの費用負担を軽減できる場合があります。
ここでは、介護保険が使える条件や具体的な申請方法をわかりやすく解説します。
保険適用となる対象者と利用目的
介護タクシーで介護保険を利用するには、要介護認定を受けていることが前提となります。
要支援1・2は対象外となることが多く、原則として要介護1以上の認定が必要です。
さらに、保険の適用は「通院」など介護保険制度で認められた目的に限られ、買い物や趣味の外出といった日常的な利用には使えません。
加えて、訪問介護の一環として運転や乗降の介助を伴う場合にのみ保険が適用され、単なる送迎依頼では全額自己負担になります。
介護保険の利用を希望する場合は、ケアマネジャーに相談し、ケアプランに該当内容を組み込んでもらう必要があるため確認しておきましょう。

介護タクシーで受けられるサービス内容と注意点
介護タクシーでは、単なる送迎にとどまらず、乗降時の介助や玄関から車両までの移動補助、病院内での受付同行など、利用者の状態に応じた多様な支援が受けられます。
車いすやストレッチャーのまま乗車できる車両も整備されており、体力に不安がある方でも安心して利用できる点が特徴です。
ただし、提供されるサービスの内容は事業者によって異なり、すべてが介護保険の対象になるとは限りません。
例えば、日常生活支援に該当する内容は自己負担となることがあります。
そのため、必要な介助や乗降の条件については事前に詳細を伝えておくことが大切です。
安心してサービスを受けるには、あらかじめ内容や注意点をしっかり把握しておきましょう。
申請手続きの流れと必要書類
介護保険を利用して介護タクシーを使うには、事前の申請手続きが必要です。
まず、要介護認定を受けていることが前提となり、ケアマネジャーと相談のうえ、ケアプランに「通院等乗降介助」の項目を加える必要があります。
その後、市区町村に利用申請を行い、許可が下りれば介護保険を適用してタクシーを利用できるようになります。
申請時には、介護保険被保険者証や主治医意見書、本人確認書類の提出が求められます。
自治体によっては、利用理由書や同意書など、追加書類が必要になることもあるでしょう。
手続きの内容や流れは地域によって異なるため、あらかじめ担当窓口で確認しておくことが大切です。
利用開始後の流れとトラブル防止のポイント
介護タクシーの利用を開始すると、定期的な通院や外出にあわせて、安定したサービスを受けられるようになります。
ただし、事業者との連携が不十分な場合には、予定どおりに送迎されないなどのトラブルが発生するおそれもあります。
こうした問題を防ぐには、予約時に目的地や乗車時刻、介助の有無などを毎回丁寧に共有し、確認することが重要です。
また、体調の変化や通院先の変更があった際には、早めに連絡することで柔軟な対応につながります
。もしドライバーとの相性や対応に不安を感じた場合には、遠慮せず事業者に相談してみてください。
介護タクシーを予約する流れと注意点
介護タクシーをスムーズに利用するためには、事前の予約手順や確認事項をしっかり押さえておくことが大切です。
ここでは、介護タクシーの予約方法と注意すべきポイントについて具体的に解説します。
予約の手段
介護タクシーの予約は、電話やFAX、インターネットなどを通じて行うのが一般的です。
地域によっては、介護タクシー専用の予約窓口が設けられていることもあり、自治体のホームページやケアマネジャーから必要な情報を得ることができます。
スマートフォンやパソコンの操作に不安がある場合は、電話での直接予約が安心です。
さらに、一部の事業者ではLINEやメールにも対応しており、日程の変更やキャンセルも手軽に行えるようになっています。
予約時には、乗車日時、出発地、目的地、介助の要否、車いすの種類などを詳しく伝えることが重要です。

当日予約はできる?可否と注意点
介護タクシーは完全予約制で運行している場合が多く、当日の予約が可能かどうかは事業者によって異なります。
空き状況によっては対応してもらえることもありますが、特に午前中や通院が集中する曜日は予約が埋まりやすく、希望どおりの手配が難しいこともあるため注意が必要です。
また、乗降介助や福祉機器の準備が必要な場合は、対応までに時間を要することもあるため、早めに連絡しておくと安心です。
急な予定変更や当日の移動が生じた際は、電話で直接問い合わせるのが確実といえます。
予定が決まっている場合には、数日前の段階で予約を済ませておくのが理想的です。
通院・リハビリ送迎など目的別の流れ
介護タクシーは、通院やリハビリなど目的に応じて柔軟に利用できる点が特長です。
通院の場合は、予約時に医療機関の場所や診療予定時刻を伝えておくことで、待ち時間を最小限に抑えた送迎が可能になります。
リハビリ通所やデイサービスを利用する際は、施設との連携が求められるため、往復送迎の有無や帰宅時間なども事前に確認しておくと安心です。
また、病院内での付き添いが必要な場合には、介助サービスの有無や追加料金が発生するかどうかも把握しておきましょう。
さらに、定期利用を前提とする場合には、スケジュールをあらかじめ組んでおくことで予約が取りやすくなります。
利用目的に応じた流れを理解し、必要な情報を正確に伝えることが、スムーズな送迎の実現につながります。
介助が必要な場合の事前相談と伝え方
介護タクシーを利用する際に介助が必要な場合は、予約時の段階で具体的なサポート内容を伝えておくことが重要です。
例えば、「自宅の玄関から車両までの移動に介助が必要」「病院の受付まで付き添ってほしい」など、支援が必要な範囲を明確に伝えることで、より適切な対応が受けやすくなります。
加えて、利用者の身体状況や使用している福祉用具(車いすの種類や杖の有無など)についても事前に説明しておくと、当日のトラブル回避につながります。
事業者によって対応可能な内容には差があるため、希望するサービスが提供可能かどうかも確認しておくと安心です。
キャンセル・変更時の対応ルール
介護タクシーを利用する際、やむを得ず予定を変更・キャンセルする場合には、事前の連絡が重要です。
多くの事業者では、前日や数時間前までに連絡すればキャンセル料が発生しないルールを設けています。
ただし、当日直前の連絡や無断キャンセルとなると、料金の一部もしくは全額が請求されることがあります。
さらに、定期利用や予約が集中する時間帯では、急な変更に対応できない場合もあるため、早めに相談することが望まれます。
体調の変化や通院予定の変更が生じた際も、迅速に連絡することで柔軟な対応につながります。
円滑な利用を継続するには、契約時にキャンセルポリシーを確認し、当日の連絡先を控えておくと安心です。
目的に応じて適切なタクシーを選ぼう
車いすを利用しての移動には、目的や身体状況に応じたタクシー選びが欠かせません。
通院や介助が必要な移動であれば介護タクシーが、短距離の外出や軽度の移動支援であればUDタクシーや一般タクシーが有力な選択肢となります。
各タクシーにはサービス内容や対応車両、料金体系に違いがあるため、事前に確認したうえで予約・利用することが安心・安全な移動につながります。
特に介助を伴う移動では、事前の相談と情報共有がトラブル防止に効果的です。
地域の制度や福祉タクシー券の活用も視野に入れながら、自身またはご家族の状況に最も合った移動手段を検討し、快適な日常生活をサポートする足として活用していきましょう。