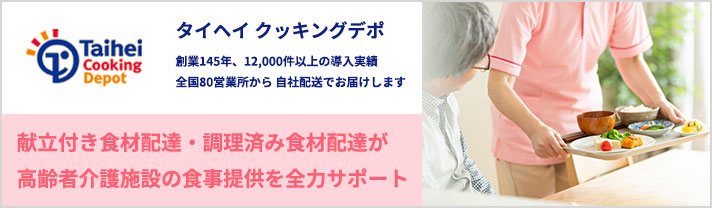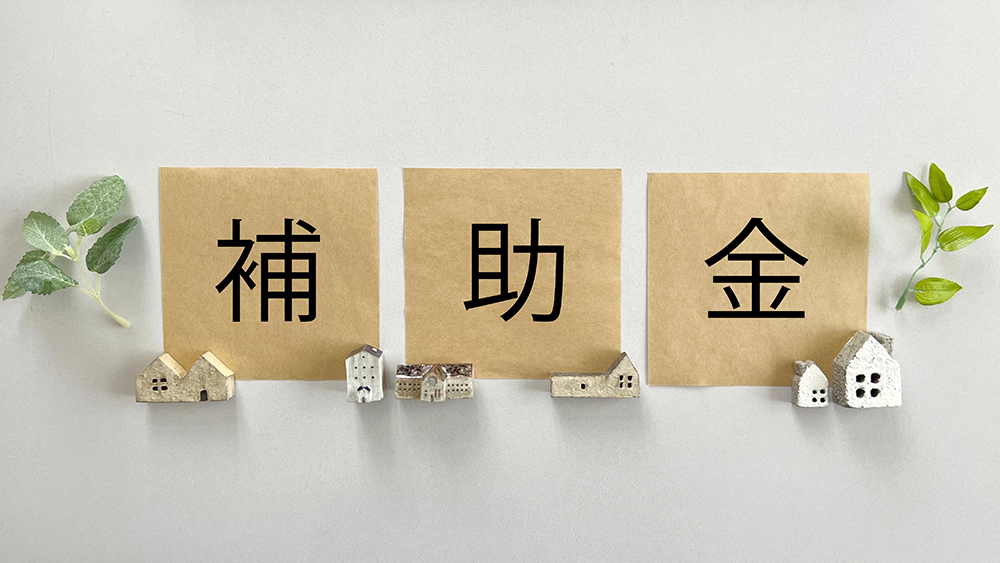- 投稿日 2025/10/24
- 更新日 2025/10/24
介護保険で車いすをレンタル|条件・流れ・費用の完全ガイド
個人旅行向け
障がい者施設様向け
高齢者施設様向け
付き添い
知識

突然、家族の介護が必要になり、車いすの利用を検討することになった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「購入とレンタルのどちらがいいの?」「介護保険は使えるの?」「どこに相談すればいいの?」と、初めての介護にはわからないことが多く、不安を感じるのは当然です。
この記事では、介護保険を活用して車いすをレンタルするための条件や手続きの流れ、費用の目安、購入との違い、さらには車いすの種類や選び方まで、やさしく丁寧に解説しています。
介護が初めての方でも安心して読み進められるよう、具体的なステップやQ&Aも交えながらご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
目次
介護保険で車いすレンタルが受けられる条件(適用基準と例外)
車いすのレンタルに介護保険を利用するには、一定の要介護度を満たす必要があります。ただし、軽度の方でも例外的に対象となるケースがあります。
「要介護2以上」の基準とは
介護保険を利用して車いすをレンタルできるのは、原則として「要介護2以上」と認定された方です。
要介護2とは、日常生活において移動・排泄・食事などで部分的に介助が必要な状態を指し、特に歩行や立ち上がりなどの動作に支援が必要とされます。
介護保険制度では、要介護2以上の認定を受けた方は、福祉用具のレンタル(車いすを含む)について自己負担1~3割で利用することができます。
この基準は「常時の利用が想定されるかどうか」という観点から定められており、歩行が困難で車いすによる移動が日常的に必要な方が対象です。
「軽度者への例外給付」とは?
一方で、要支援1・2や要介護1といった比較的軽度の方でも、例外的に車いすのレンタルが認められる場合があります。
これを「軽度者への例外給付」と呼びます。
これは、医師の意見書やケアマネジャーの判断をもとに、市区町村が「福祉用具の使用がやむを得ない」と判断した場合に限って適用されます。
たとえば、骨折や疾病によって一時的に歩行が困難になった場合や、自宅の構造上、転倒のリスクが高く移動に介助が必要な場合などが該当します。
この例外措置を受けるには、ケアマネジャーに相談し、適切な手続きと判断を経る必要があります。
自己判断でレンタルを始めるのではなく、専門職と連携しながら進めることが重要です。
レンタルのメリットと購入との比較ポイント
車いすの利用を考える際、レンタルと購入のどちらがよいか迷う方も多いでしょう。
それぞれに特徴があり、利用期間や目的に応じて選ぶことが大切です。
費用面の比較(レンタル vs 購入)
車いすの購入費用は、自走式でおおよそ2万円から5万円程度、電動車いすでは10万円〜20万円を超えるものもあります。
一方、介護保険を利用したレンタルでは、車いすの種類にもよりますが、月額3,000〜6,000円が相場です。
介護保険の自己負担割合が1割であれば、月額300〜600円ほどで利用できます。
レンタルは短期間の利用に特に向いており、たとえば「退院後の一時的なリハビリ期間」や「旅行時の使用」といったケースでは、購入よりも大幅に費用を抑えられます。
ただし、長期間の使用が見込まれる場合は、購入した方が結果的に安く済むこともあるため、利用期間の見込みも踏まえて検討することが重要です。
使い勝手・柔軟性の比較
レンタルの最大のメリットは、使い勝手や柔軟性に優れている点です。
利用者の体調や生活環境が変化した際には、車いすの種類を変更したり、サイズや仕様を見直したりすることが可能です。
ケアマネジャーや福祉用具専門相談員が定期的にモニタリングを行い、必要に応じて機種の入れ替えや調整をサポートしてくれます。
さらに、レンタル品は事業者によって定期的なメンテナンスが行われており、故障時の対応や部品交換もスムーズです。購入の場合、修理や部品の交換は自己負担になるため、負担が大きくなる可能性があります。
とくに高齢の利用者にとっては、安心して使い続けられる体制が整っているレンタルの方が適していることも多いです。
レンタル開始までの流れと必要な手続き
介護保険を使って車いすをレンタルするには、いくつかの手続きが必要です。
要介護認定から契約・納品までの一連の流れを知っておくことで、スムーズに準備を進められます。
要介護認定の申請とケアプラン作成
まず、介護保険を使って車いすをレンタルするには、「要介護認定」を受ける必要があります。
これは、市区町村の窓口や地域包括支援センターで申請できます。
申請後、認定調査員による訪問調査と医師の意見書の提出が行われ、通常1か月ほどで要介護度が決定されます。
認定結果が出たら、ケアマネジャーと相談しながら「ケアプラン(介護サービス計画)」を作成します。
このケアプランには、車いすレンタルの必要性や利用目的が反映されます。
ケアマネジャーがいない場合は、地域包括支援センターで紹介を受けることができます。
ここまでのステップが完了すると、福祉用具のレンタル手続きへと進みます。

医師の意見書と事業者選定、契約、納品まで
要介護認定の申請と並行して、かかりつけ医の診察を受け、「主治医意見書」を作成してもらう必要があります。
この意見書は、車いすの必要性や利用目的を明示するもので、市区町村が認定を判断する際の重要な資料となります。
認定が下り、ケアプランに車いすレンタルが盛り込まれたら、福祉用具貸与事業者を選定し、契約に進みます。
事業者との契約が成立すると、スタッフが自宅まで車いすを届けてくれ、使用方法や注意点の説明を行ってくれます。
利用後も定期的に点検や相談対応が行われ、必要に応じて機種変更や調整が可能です。
自己負担額の目安と費用シミュレーション
介護保険を利用した車いすレンタルでは、自己負担額は利用者の所得や車いすの種類によって異なります。
ここでは具体的な金額例と、負担割合による違いを解説します。
月額レンタル料金の具体例
介護保険を活用した車いすのレンタルでは、車いすの種類によりレンタル料金が異なります。
たとえば、自走式の車いすは月額3,000〜5,000円、介助式では2,000〜4,000円程度が相場です。
電動車いすは高額で、月額20,000〜30,000円になることもあります。
この費用に対し、介護保険が適用されることで自己負担は1〜3割に抑えられます。
たとえば、月額5,000円の車いすを借りる場合、1割負担であれば月々500円、2割負担なら1,000円、3割負担でも1,500円と、非常にリーズナブルに利用できます。
これは一時的な使用だけでなく、長期的な利用にも大きな経済的メリットとなります。
自己負担割合による比較
自己負担割合は、利用者の所得に応じて1割・2割・3割のいずれかに区分されます。
一般的に、住民税非課税世帯や年金収入のみの高齢者は1割負担が適用されるケースが多く、高所得者層では2割または3割となる場合があります。
同じ車いすでも、負担割合によって支払う金額は大きく異なります。
たとえば、月額6,000円の電動車いすを借りる場合、1割なら600円、3割なら1,800円の支払いが必要になります。
また、要介護度によっては、利用できる福祉用具の種類に制限があるため、ケアマネジャーとよく相談することが重要です。
制度による軽減措置があるとはいえ、自己負担額の差は長期的に見れば大きな影響を与えます。
レンタル開始前に、必ず自身の負担割合を確認し、無理のない範囲でサービスを活用しましょう。
車いすの種類と選び方のポイント
車いすには複数の種類があり、利用者の身体状況や使用環境に応じて選ぶことが重要です。
ここでは代表的なタイプの特徴と、選び方のポイントを紹介します。
自走式・介助式・電動車いすの違い
車いすは大きく分けて「自走式」「介助式」「電動式」の3つがあります。
自走式車いすは、利用者本人が車輪を操作して移動するタイプで、自立した移動が可能な方に適しています。

一方、介助式車いすは後部にあるハンドルを介助者が操作する設計で、利用者の体力や腕力が不十分な場合に適しています。
軽量でコンパクトなものが多く、屋内や施設内での移動に便利です。
そして、電動車いすは、モーターによって駆動し、ジョイスティックなどで操作します。
歩行困難で長距離の移動が必要な方に向いており、操作に慣れることで屋外の活動範囲を広げることも可能です。
ただし、重量や費用、保管スペースに注意が必要です。
使用シーン・身体状況に応じた選び方
車いす選びでは、利用者の身体状況や使用環境に合わせた選定が重要です。
以下のポイントを参考にしましょう。
- 体力があるが足腰に不安がある方:自走式が最適。自立性を維持しながら移動できます。
- 筋力が弱く、自力での操作が難しい方:介助式がおすすめ。軽量で介助者の負担も軽減されます。
- 長距離移動や屋外利用が多い方:電動車いすが便利。ただし、充電管理や操作の習熟が必要です。
また、居住空間の広さや段差の有無、収納スペースの確保なども考慮すべき点です。
福祉用具専門相談員が同行して、実際に使用する環境に合った機種を提案してくれるサービスもあるため、積極的に相談することをおすすめします。
介護保険が使えないケースと自費レンタルの対応方法
介護保険が使えないケースでも、車いすの利用をあきらめる必要はありません。
ここでは、よくある非適用パターンとその際の代替手段を解説します。
要介護認定されなかった場合
要介護認定を申請しても、「非該当」または「要支援1・2」と判断された場合、原則として介護保険による車いすレンタルの対象外となります。
特に歩行がある程度可能とみなされた場合や、日常生活動作が軽度な方は、制度上の制限で利用が認められないことがあります。
しかし、そのような場合でも車いすが必要な状況は多く存在します。
その際は、自費でのレンタルを検討することが現実的な選択肢です。
介護ショップや医療機器専門店などで、1日単位や1か月単位でレンタルできるサービスがあり、料金も2,000~8,000円程度で種類によって変動します。
また、市区町村によっては、要介護認定を受けていなくても、特定の条件下で助成金や補助制度が用意されていることがあります。
地域包括支援センターに相談し、利用可能な支援を探ることが重要です。
一時的に使用したいが保険対象外なとき
ケガや手術後の短期間の使用、旅行や外出など一時的な目的で車いすを使いたい場合も、介護保険の対象外となることがあります。
こうしたケースでは、自費レンタルのフレキシブルな活用が適しています。
たとえば、退院直後の1~2週間だけ使いたい場合や、介護認定をまだ受けていないが不自由を感じている期間などは、短期レンタルサービスが便利です。
民間の福祉用具貸与事業者では、1日単位でのレンタルや「お試し利用」プランを提供しているところもあり、介護保険の手続きなしで即日対応してくれる場合もあります。
このような自費レンタルは、費用は全額自己負担になりますが、手続きが簡便で、必要なときにすぐ使えるという点で大きな利点があります。
必要期間が短い場合は、購入よりも経済的な選択になることも多いです。
車いすレンタル事業者の選び方と確認ポイント
車いすをレンタルする際には、事業者の選定が非常に重要です。
ここでは、信頼できる事業者を選ぶための視点と、契約前に確認すべきポイントを紹介します。
地域密着型と全国展開の違い
車いすレンタルを行っている事業者には、大きく分けて「地域密着型」と「全国展開型」の2種類があります。
どちらにもメリットがあり、利用者の状況によって選ぶべき事業者が異なります。
地域密着型の事業者は、迅速な対応と柔軟なサービスが魅力です。
訪問対応や細かい調整、トラブル時の素早い対応が期待できるため、高齢者や自宅での介護が中心となる方にとって安心感があります。
一方で、取り扱っている車いすの種類が限られていることもあります。
全国展開している事業者は、在庫数が豊富で最新機種の取り扱いも多く、広域での引っ越しや旅行時の対応にも強みがあります。
ただし、エリアによっては対応が遅れることもあるため、サービス内容を事前に確認することが大切です。
契約前に確認すべきこと
事業者と契約を結ぶ前に、以下のポイントをしっかり確認しておくことがトラブルを防ぐカギとなります。
- 月額レンタル料と自己負担額:介護保険適用後の自己負担額(1割~3割)を明示してもらいましょう。
- 機種変更・サイズ交換の可否:体調や生活環境の変化に応じた対応が可能かを確認します。
- メンテナンス・修理対応:故障や不具合が発生した場合、どれくらいのスピードで対応してくれるか、無料かどうかも重要です。
- 利用開始・終了の手続き:契約の流れや、解約時の取り扱い(返却手順・違約金の有無など)も事前に確認しておきましょう。
また、担当する福祉用具専門相談員の資格や対応力も選定のポイントです。
説明が丁寧で、利用者の状態や環境に寄り添った提案ができる事業者を選ぶと、長期的に安心して利用できます。

状況別おすすめアクション例
車いすが急に必要になったときや、長期間の使用が想定されるときなど、状況によって最適な対応は異なります。
ここでは代表的な2つのケースを紹介します。
申請中でも自費レンタルを始めたいとき
介護保険の申請中で、まだ要介護認定が下りていない場合でも、車いすが今すぐ必要になることがあります。このようなケースでは、2つの対応策が考えられます。
1つ目は、「暫定ケアプラン」を作成して、介護保険適用のレンタルを一時的に始める方法です。
これはケアマネジャーと相談し、要介護認定の結果が出る前に、仮の計画でサービスを開始するものです。認定が下りて条件を満たせば、そのまま継続利用が可能となります。
2つ目は、「全額自費でレンタルを開始する方法」です。
認定結果で非該当となった場合、保険が適用されないため、利用期間分の費用を全額自己負担する必要があります。
負担は増えますが、すぐに車いすを必要とする緊急時には有効な手段です。
長期間使う場合、購入を検討すべきケース
利用期間が半年〜1年以上など長期にわたると見込まれる場合は、レンタルより購入の方がコスト面で有利になることがあります。
特に自己負担割合が3割の方や、電動車いすのようにレンタル費用が高額な場合には、費用シミュレーションを行って慎重に判断することが大切です。
たとえば、月額5,000円のレンタル料に対し3割負担の場合、1年間で支払う自己負担額は18,000円になります。2年・3年と続けば、低価格帯の車いすであれば購入価格を超えることもあります。
さらに、家族内で継続的に使用する可能性がある場合や、旅行・外出用として別途1台確保したいときなど、購入の利便性は高まります。
一方で、成長期のお子さまや症状が変化しやすい方には、柔軟な対応ができるレンタルが向いています。
使用頻度、身体状況の変化、生活環境を総合的に見て、どちらが適しているかを判断しましょう。
よくある質問
介護保険を使った車いすレンタルには、実際の現場でよく聞かれる疑問や不安があります。
ここでは特に多い質問をQ&A形式でご紹介します。
入院中でもレンタルは継続できる?
原則として、短期入院であれば車いすレンタルは「一時中断(休止扱い)」となり、返却する必要はありません。
この場合、レンタル料は発生しないか、または休止扱いで減額されるケースもあります。
ただし、長期入院や施設入所が前提となる場合は、介護保険のレンタル対象外と判断されることがあり、車いすをいったん返却するよう指導される場合もあります。
また、入院中に車いすを病院内で使用したい場合、病院側が備品として貸し出すケースが多いため、外部からのレンタル持ち込みが制限されることもあります。
事前に病院やレンタル事業者に確認しておくと安心です。
旅行時のレンタル利用は可能?
旅行や一時的な外出に際して、車いすを持ち出すことは原則として可能です。
ただし、注意点としては「保険適用範囲」と「紛失・破損時の補償」です。
通常の介護保険レンタルは、利用者の自宅での使用が前提とされていますが、旅行先での使用も事前申請や許可を取ることで対応可能なケースが多いです。
また、旅行先のホテルや施設では、搬入・搬出の制約や、事業者の対応エリア外になる場合もあるため、出発前にケアマネジャーや事業者に相談して計画的に進めましょう。
必要に応じて、現地の一時レンタルサービスを利用することも選択肢のひとつです。
ケアマネに相談して車いすレンタルの第一歩を踏み出そう
介護保険を利用した車いすレンタルは、制度の活用次第で経済的・実用的に非常にメリットのある選択肢になります。
まずはケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、ご自身やご家族の状況に合った対応を進めていきましょう。
制度の対象外であっても自費レンタルや助成制度など、選択肢は決して一つではありません。
この記事で得た情報をもとに、最初の一歩を踏み出してみてください。
必要であれば、関連記事や自治体の公式サイトもあわせて確認し、より良い介護環境づくりにつなげていきましょう。