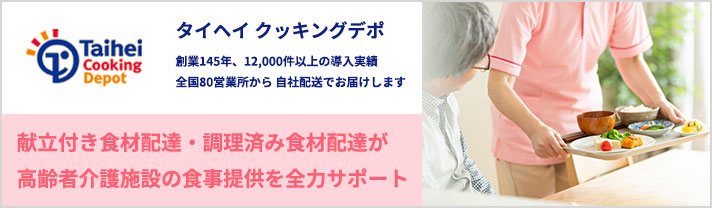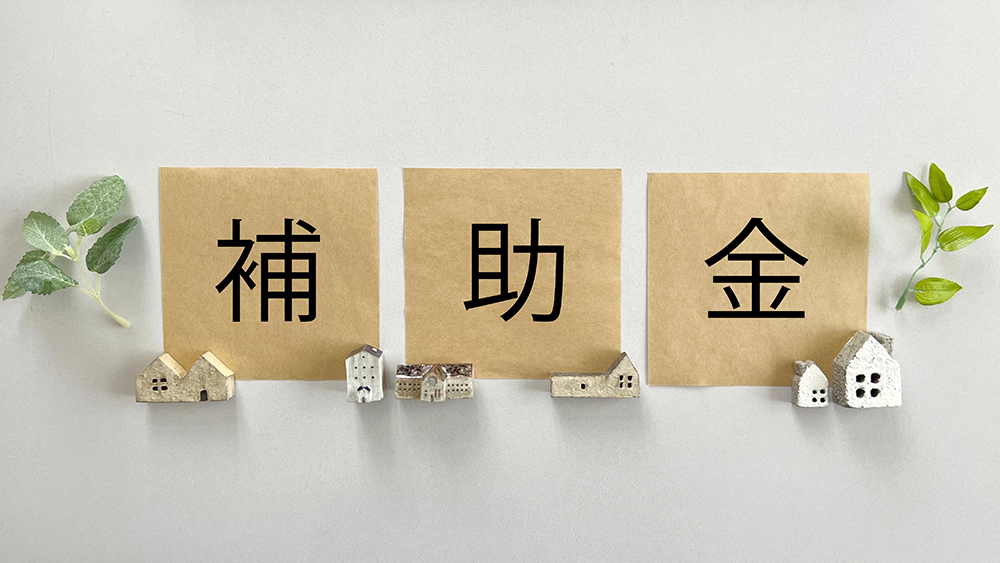- 投稿日 2025/06/11
- 更新日 2025/08/01
エリア別に見る身近なバリアフリー例16選|旅行時にチェックしておきたいポイントも紹介
個人旅行向け
知識

バリアフリーという言葉はよく聞くものの、実際にどのような配慮がなされているのかを具体的にイメージできない方も多いのではないでしょうか。車いすの利用や視覚・聴覚の障がいがある方にとって、日常生活や旅行中の小さな段差や情報の伝わりにくさは大きな壁になり得ます。
そこで今回は、住宅・街・交通機関といった身近な場所でのバリアフリー事例を紹介し、旅行時に役立つ確認ポイントも詳しく解説します。
目次
バリアフリーとは?4つのバリアとユニバーサルデザインとの違い
バリアフリーという言葉はよく耳にしますが、具体的にどのような意味があり、どんな考え方にもとづいているかをご存知でしょうか。ここでは、バリアフリーの基本的な定義に加え、生活の中で直面しがちな「4つのバリア」、そして混同されやすいユニバーサルデザインとの違いについてもわかりやすく解説します。
バリアフリーとは?
バリアフリーとは、高齢者や障がいのある方を含むすべての人が、日常生活を支障なく送れるようにするための考え方です。具体的には、移動・利用・参加といったあらゆる場面で、物理的・制度的・心理的な障壁を取り除くことを指します。
例えば、段差の解消や手すりの設置、見やすく工夫された案内表示などがその一例です。車いすや白杖を使用する方にとっては、わずかな段差や扉の構造が移動の妨げになることもあるため、こうした配慮は非常に重要です。
福祉施設や介護の現場においても、日々の暮らしを安全かつ快適に過ごせるよう、住宅や街全体のバリアフリー化が進められています。建築的な対応だけでなく、一人ひとりの状況に寄り添った配慮が求められる点も特徴です。

4つのバリアとは?
バリアフリーを考えるうえで、私たちの生活に影響を与える「4つのバリア」について理解しておくことが重要です。
まず「物理的バリア」は、段差や狭い通路など、移動や利用を妨げる構造上の障壁を指します。「制度的バリア」は、制度やルールが障がいのある方にとって不利に働いてしまう状態のことです。
「情報的バリア」は、視覚や聴覚に障がいがある方に必要な情報が届かない、あるいは理解しづらい環境を意味します。そして「心のバリア」とは、無理解や偏見といった人々の意識の中にある壁です。
ユニバーサルデザインとの違い
バリアフリーとよく似た概念に「ユニバーサルデザイン」がありますが、目的やアプローチには明確な違いがあります。
バリアフリーは、高齢者や障がいのある人が日常生活で直面する「障壁(バリア)」を取り除くための対応です。すでに存在する不便さに対して「後付け」で対策を講じるケースが多い点が特徴といえます。
一方、ユニバーサルデザインは、年齢や障がいの有無に関わらず、すべての人が最初から使いやすいように設計する考え方です。例えば、段差のない入口や軽く押すだけで開く自動ドアは、誰にとっても便利で使いやすい構造です。
エリア別に見るバリアフリーの実例(住宅・街・交通)
バリアフリーは、住まいの中だけでなく、街なかや公共交通機関にも広がりつつあります。ここでは「住宅」「街」「交通」の3つの場面に分けて、身近に見られるバリアフリーの具体例を紹介します。
住宅で見られるバリアフリーの実例
まずは、実際に住宅で採用されているバリアフリーの事例を紹介します。
玄関にスロープが設置されている
玄関にスロープがある住宅は、バリアフリーの代表的な事例といえます。段差のある玄関は、車いす利用者や足腰に不安のある人にとって大きな障壁になりますが、スロープが設けられていれば、出入りがスムーズに行えます。
また、ベビーカーや歩行器を使用する人にとっても利便性が高く、家族全員にとって安心できる設備といえます。スロープの勾配や幅、手すりの有無といった設計要素は、使いやすさや安全性に大きく影響します。実際の住宅では、転倒防止の工夫や、素材選びにも配慮されているケースが多く見られます。

こうしたスロープの設置は、屋内外の移動をサポートするだけでなく、利用者自身の自立を促す役割も担っています。
室内の扉が引き戸になっている
室内の扉が引き戸になっている住宅も、バリアフリー設計の代表的な工夫の1つです。開き戸と異なり、引き戸は前後のスペースを必要としないため、車いすや歩行器の利用者でもスムーズに通行できます。
体の向きを変えずに開閉できるため、腕の可動域に制限がある方や介助中の場面でも扱いやすい点もメリットです。さらに、敷居に段差がない構造になっているものも多く、つまずきの防止にもつながります。
また、軽い力で開閉できるタイプや、自動でゆっくり閉まる設計など、利用者の負担を減らす工夫が施されている点も特徴です。
廊下や浴室に手すりが付いている
廊下や浴室に手すりが設置されている住宅も、バリアフリー設計が施された住宅といえます。手すりがあることで、歩行に不安のある方や高齢者、体に障がいのある方でも体を支えながら安心して移動できます。
廊下や浴室に手すりが設置されている住宅も、バリアフリー設計が施された住宅といえます。手すりがあることで、歩行に不安のある方や高齢者、体に障がいのある方でも体を支えながら安心して移動できます。

浴室にシャワーチェアや滑りにくい床材が使われている
浴室にシャワーチェアや滑りにくい床材が使われている住宅も、バリアフリー設計の一例としてよく見られます。
シャワーチェアは、立ち姿勢を保つのが難しい方や、長時間の入浴が負担になる方にとって、座ったまま安全に洗身や洗髪ができるようサポートしてくれる便利な道具です。
また、浴室の床が滑りにくい素材になっていることで、石けんや水による転倒のリスクを抑えられます。段差が少ない設計や出入口の開口幅が広い構造が採用されている場合もあり、介助する人の動きやすさにも配慮されています。
トイレに介助スペースや手すりが確保されている
トイレに介助スペースや手すりが確保されている住宅も、バリアフリーにおける基本的な配慮の1つです。
車いすのまま入れる十分な広さがあれば、移乗動作や介助者のサポートもスムーズに行えます。手すりは、立ち上がりや姿勢の保持を助けるために重要で、L字型や縦型など、用途に応じた形状が採用されることが一般的です。
介助スペースがあることで、必要な支援を無理なく行えるだけでなく、利用者にとっても安心して使える環境になります。加えて、ドアの開閉方式、便座の高さ、ペーパーホルダーの位置といった細部も、使いやすさを左右する大切な要素です。
ベッドまわりに十分なスペースがあり、車いすでも利用しやすい
バリアフリー設計においては、ベッド周辺に十分なスペースを確保することが重要です。車いすを使用する場合、ベッドの横や足元にゆとりがあることで、方向転換や移乗の動作がしやすくなります。
介助が必要な方にとっても、ベッドの片側に人が立てるだけのスペースがあると、無理のない体勢で支援しやすくなります。また、ベッドの高さが車いすの座面と近い場合、移動時の負担も軽減されます。
照明スイッチや呼び出しボタンが手の届く範囲にあるかどうかも、日常生活の利便性に直結するポイントです。
このように、ベッドまわりの空間設計には、使用者の自立を促し、安全性や介助のしやすさを高める意図が込められています。
街なかで見られるバリアフリーの実例
次に、誰もが安心して過ごせる街づくりに向けた具体的な取り組みを紹介します。
スロープや段差解消板が設置されている
街なかで見かけるスロープや段差解消板は、歩道の縁石や建物の出入口など、高低差のある場所に設けられるバリアフリー設備の1つです。車いすやベビーカーを利用する人、足元に不安のある高齢者にとって、段差は移動を妨げる要因であり、つまずきや転倒のリスクも伴います。
街なかで見かけるスロープや段差解消板は、歩道の縁石や建物の出入口など、高低差のある場所に設けられるバリアフリー設備の1つです。車いすやベビーカーを利用する人、足元に不安のある高齢者にとって、段差は移動を妨げる要因であり、つまずきや転倒のリスクも伴います。
勾配の緩やかさや滑りにくい素材など、安全面への配慮も重要です。
音響式信号機が設置されている
音響式信号機は、視覚に障がいのある方が安心して道路を横断できるよう設置されたバリアフリー設備の1つです。青信号の間に「ピヨ」や「カッコー」といった音が鳴り、進行方向や信号の切り替わりを音で知らせてくれます。
交差点の規模や周囲の騒音状況に応じて音量が自動で調整されるタイプもあり、夜間には近隣への配慮として音を停止できる時間帯を設けているケースもあります。また、一部の信号機には、専用の押しボタンやリモコンで音を鳴らせる機能が搭載されています。
こうした設備は、視覚障がい者の安全な移動を支えるだけでなく、同行する家族や支援者にとっても心強い存在です。

多目的トイレが設置されている
多目的トイレは、車いすの使用者や高齢者、介助が必要な方など、さまざまな利用者に対応できるよう設計されたトイレです。一般的な個室よりも広い空間が確保されており、車いすでの出入りや方向転換もスムーズに行えます。
L字型や縦型の手すり、オストメイト対応の設備、介助者が同伴できる広さなど、利用者の状況に応じた機能が整っている点が特徴です。さらに、緊急時に備えて呼び出しボタンが設置されているケースもあり、万が一の際にも安心感があります。
こうした多目的トイレは、商業施設や公共施設などの1階や出入口付近など、アクセスしやすい場所に設置されていることが多く、街なかを移動する際の重要なチェックポイントの1つです。
バリアフリー対応の駐車場が確保されている
バリアフリー対応の駐車場は、車いす利用者や歩行が不自由な方が、安全かつスムーズに車の乗り降りができるよう配慮された駐車スペースです。一般的な区画より幅が広く、車いすの移動やスロープの展開にも十分な余裕があります。
また、建物の入口付近など、できるだけ移動距離が短くなるよう配置されていることが多い点も特徴です。地面には「車いすマーク」などの視認性の高い表示が施されており、専用スペースであることがひと目でわかります。
一部の施設では、障害者手帳の提示や事前登録が必要になるなど、利用に制限が設けられている場合もあります。現地の案内やルールを確認したうえで、正しく利用することが大切です。

案内表示にピクトグラムが使われている
街なかの案内表示にピクトグラム(絵記号)が使われていることも、バリアフリーの1つです。
トイレやエレベーター、非常口などの設備を示す際に、誰でも直感的に意味を理解できるよう、国際的に共通したシンボルが用いられています。文字による案内と比べて、言語や読解力に関係なく情報を伝えられるため、視覚障がいや知的障がいのある方、外国人旅行者などにも役立ちます。
また、ピクトグラムの色のコントラスト、表示位置、サイズなども視認性に影響する大切な要素です。最近では、点字や音声案内と組み合わせた多機能な案内システムも増えており、情報の取得を支援する取り組みが広がっています。
交通機関におけるバリアフリーの実例
交通機関にもさまざまなバリアフリーの取り組みが進められています。以下では、具体的な設備の例を紹介します。
駅構内に音声案内や案内表示が設置されている
駅構内に設置されている音声案内や視覚的な表示は、バリアフリー対応の一環として重要な役割を担っています。
視覚障がいのある方に対しては、ホームや改札、乗り換えルートを音声で案内するスピーカーが設置されており、安全な移動を支援します。
一方で、聴覚障がいのある方には、行き先や発車時刻、遅延情報などを表示するディスプレイやLED掲示板が活用されており、視認性に配慮された設計が特徴です。
近年では、多言語対応やピクトグラムを組み合わせることで、外国人や高齢者にも伝わりやすい表示が増えています。さらに、触知案内板や点字ブロックといった設備との連携により、誰もが利用しやすい駅づくりが進められています。
ホームにホームドアや可動ステップが設置されている
駅のホームに設置されたホームドアや可動ステップは、転落や乗降時の事故を防ぐバリアフリー設備として重要な役割を担っています。ホームドアは、列車の停止中にのみ開閉する仕組みになっており、視覚に障がいのある方や認知機能に不安のある方にとって、ホームからの転落を防ぐ有効な安全対策です。
一方、可動ステップは列車とホームの隙間や段差を自動で埋めることで、車いすや歩行器を使う方でもスムーズに乗り降りできるよう配慮されています。駅によっては、ホームドアと可動ステップの両方を設置することで、さらなる安全性の向上を図る取り組みも進んでいます。
鉄道は日常の移動手段として欠かせない存在であり、こうした設備の有無は利用者の行動範囲や安心感に大きく影響します。

車両内に優先席や車いすスペースが確保されている
公共交通機関の車両内には、優先席や車いすスペースが設けられており、移動に不安のある方や障がいのある方でも安心して利用できるよう配慮されています。
優先席は、高齢者や妊婦、体に障がいのある方などの利用を想定し、出入口付近や乗り降りしやすい位置に配置されています。車いすスペースには、固定用のベルトや転倒防止の支えが備え付けられており、走行中でも安全に過ごせる設計です。
また、周囲には音声案内や表示による案内もあり、視覚や聴覚への配慮も行き届いています。こうした設備の整備は、利用者同士が思いやりを持って行動するきっかけにもなり、すべての人にとって快適な車両空間の実現につながります。

バスにスロープ板やノンステップ構造が採用されている
バスにスロープ板やノンステップ構造が採用されていると、車いすを利用する方や足元に不安のある方でも、乗り降りがしやすくなります。ノンステップバスは床が低く設計されており、地面との段差が少ないため、ステップを上がる動作をせずに乗車できます。
さらに、必要に応じて運転手がスロープ板を展開することで、車いすや歩行器を使用している方の乗降もスムーズに行えます。車内には、出入口付近に車いす用のスペースや固定装置が設けられていることが多く、移動中の安全性にも配慮されています。
バスは日常の移動手段として利用頻度が高いため、こうした構造の有無は移動の自由度に大きく影響します。
飛行機や新幹線で車いす対応の座席やトイレが用意されている
飛行機や新幹線では、車いすを利用する方が快適に移動できるよう、専用の座席やトイレが用意されています。座席は通路側に配置され、周囲にゆとりがある設計となっているため、乗り降りがしやすく、安定して座れるよう配慮されています。
トイレも車いすのまま入れる広さが確保されており、介助者と一緒に利用しやすい設計がなされているのが特徴です。また、新幹線の一部車両には、スロープや昇降リフトが備えられている場合もあり、駅との段差を解消する工夫も見られます。
さらに、事前に申し出ることでスタッフによる乗降サポートが受けられる体制も整っており、長距離移動の不安を軽減する助けとなります。
旅行前にチェックしておきたい宿泊施設でのバリアフリー
安心して宿泊先を利用するためには、バリアフリー対応の状況を事前に確認することが大切です。ここでは、宿泊施設選びの際にチェックしておきたいポイントを項目ごとに紹介します。
玄関や館内に段差がないか確認しよう
宿泊施設を選ぶ際は、玄関や館内に段差がないか事前に確認しておくことが大切です。たとえ数センチの段差でも、車いすや歩行器を使う方にとっては、大きな障害となることがあります。
段差がスロープで解消されているか、床がフラットに保たれているかをチェックしましょう。館内の移動経路に階段や敷居がないか、エレベーターが設置されているかどうかも重要な確認ポイントです。
特に館内が広い場合は、段差の連続や滑りやすい床材が移動のしやすさに影響を与える可能性があります。施設のホームページに段差やバリアフリー設備についての記載がない場合は、電話などで直接問い合わせるのが安心です。
多目的トイレや浴室の設備を確認しよう
宿泊施設を選ぶ際は、多目的トイレや浴室の設備が整っているかを事前に確認しておきましょう。
車いすの利用を想定した多目的トイレには、十分なスペースのほか、L字型の手すりや緊急呼び出しボタンが備えられていることが多く、安全面への配慮がなされています。排泄時の姿勢保持や緊急時の対応がしやすい点が特徴です。
浴室についても、滑りにくい床材が使われているか、シャワーチェアが用意されているかなど、転倒リスクを減らす工夫が重要です。また、浴槽への移乗がしやすい構造か、介助者が一緒に入れる広さが確保されているかどうかも確認しておくと安心です。
入浴や排泄といったプライベートな場面に関わる設備は、利用者の尊厳や快適さに直結します。だからこそ、細かな部分まで丁寧に確認することが大切です。
写真や備品の情報は、施設のホームページやパンフレットなどで事前にチェックしましょう。

車いす対応の客室かどうかを確認しよう
宿泊先を選ぶ際は、車いすに対応した客室が用意されているかも事前に確認しておきましょう。ベッドまわりに十分な回転スペースがあるか、トイレや浴室へスムーズに移動できるかといった点は、快適な滞在のために欠かせません。
出入口の幅が車いすで通れる広さかどうか、室内に段差がないか、家具の配置が移動の妨げになっていないかも確認したいポイントです。さらに、介助者が同室で過ごす場合には、介助しやすい動線や設備が整っているかどうかも重要です。
「バリアフリールーム」と記載されていても、その設備内容には施設ごとに差があるため、写真や設備一覧を見て具体的にチェックしましょう。不明点がある場合は、事前に施設へ問い合わせると安心です。
視覚・聴覚への配慮があるかチェックしよう
視覚や聴覚に障がいのある方が安心して宿泊できるよう、情報の伝わり方に配慮があるかも事前に確認しておきましょう。
視覚に障がいのある方には、点字による案内表示や音声ガイド、触知図などが有効です。館内放送だけに頼らず、個別に対応できるサポート体制が整っているかどうかも確認したいポイントです。
一方、聴覚に障がいのある方にとっては、筆談での対応やフロントでの筆記具の用意、光で知らせるインターホンや火災報知器などの設備があると安心です。
最近では、スマートフォンを活用した多言語・音声対応のアプリを導入している施設も増えています。

交通機関や送迎手段がバリアフリー対応か確認しよう
旅行を計画する際は、現地までの交通機関や宿泊施設の送迎手段がバリアフリーに対応しているかも、あらかじめ確認しておきましょう。
駅やバス停では、エレベーターやスロープ、可動ステップ付きの車両が整備されているかどうかが重要です。バスやタクシーなどの送迎サービスについても、リフト付き車両や車いすスペースの有無を事前に確認しておく必要があります。
こうしたサービスは、予約が必要な場合も多いため、出発前にしっかりと調整しておくと安心です。加えて、乗降時のサポート体制やスタッフによる介助が受けられるかどうかも、施設や交通機関に直接問い合わせておくとよいでしょう。
バリアフリー旅行を成功させるためのポイント
バリアフリー旅行を快適に楽しむためには、出発前の準備がとても重要です。ここでは、旅行をスムーズに進めるために押さえておきたい実践的なポイントを順を追って解説します。
移動手段と交通機関のバリアフリー対応を確認しよう
移動手段を選ぶ際は、目的地までの交通機関がバリアフリーに対応しているかも事前に確認することが大切です。
例えば、駅構内にはエレベーターや音声案内、点字ブロックが整備されているかをチェックしましょう。バスや電車では、乗降しやすいスロープや可動ステップが備えられているかも重要な確認項目です。
あわせて、車いすスペースや優先席の有無、スタッフによるサポート体制の有無にも注目しましょう。飛行機や新幹線を利用する場合は、バリアフリー座席の配置やトイレの広さも確認しておくと安心です。
また、送迎バスやタクシーがリフト付きかどうか、予約が必要かどうかも事前に把握しておくとスムーズです。

宿泊施設の設備とサポート体制を事前に調べよう
快適な旅を実現するには、宿泊施設のバリアフリー対応状況を事前に確認しておくことも大切です。
玄関や館内に段差がないか、エレベーターが設置されているかといった基本的な設備に加え、多目的トイレや浴室の使いやすさ、車いす対応の客室の有無も確認しておきましょう。緊急時に備えた呼び出しボタンや手すりの配置など、安全面への配慮も見逃せません。
また、スタッフによる介助対応の可否や、チェックイン時の案内、食事の際のサポートといった「人的支援」が整っているかどうかも、安心して宿泊するうえで重要なポイントです。
公式サイトの情報だけではわからない場合は、電話やメールで直接問い合わせてみるのがおすすめです。
食事の内容や提供方法にも配慮しよう
旅先での食事は楽しみの1つですが、障がいのある方にとっては、内容や提供方法への配慮が欠かせません。アレルギー対応や刻み食、ミキサー食などの希望に応じてもらえるかどうかは、事前に宿泊施設へ確認しておくと安心です。
また、食事会場までの動線に段差がないか、テーブルの高さや椅子の形状が車いすで利用しやすいかも、重要なチェックポイントとなります。
視覚に障がいがある方には、料理の説明や盛り付けの工夫、食器の配置など、情報面でのサポートも求められます。
こうした細やかな配慮が、食事の時間を心地よく過ごすことにつながります。
利用者の体調や障がい特性に合わせた行程を組もう
バリアフリー旅行を計画する際は、利用者の体調や障がいの特性を考慮し、負担の少ない行程を立てることが大切です。移動時間が長すぎたり、観光地での滞在時間が短すぎたりすると、心身に大きな負担がかかる場合があります。
適度に休憩を挟むタイミングや、バリアフリー対応のトイレや休憩所の位置は、事前に確認しておくと安心です。また、感覚過敏や疲れやすい方にとっては、人混みを避けた時間帯の移動や、静かな環境を選ぶといった配慮も有効です。
本人や介助者とよく相談しながら、ゆとりあるスケジュールを立てましょう。
万が一のためにサポート体制や保険を確認しよう
バリアフリー旅行では、思わぬ体調不良やトラブルが起きたときに備えて、事前にサポート体制や保険の内容を確認しておくことも大切です。宿泊施設や交通機関が緊急時にどのような対応を行ってくれるのか、また近隣の医療機関の場所や連絡手段も把握しておくと安心です。
旅行保険についても、一般的な補償だけでなく、介助者の同行費用や旅行のキャンセル補償、医療搬送に関する特約が含まれているかを確認しましょう。同行者が家族や福祉職員であっても、対応できる範囲には限りがあります。そのため、専門機関によるサポート窓口があるとより心強いです。
「万が一」を想定した備えがあれば、不安の少ない快適な旅につながります。
一人ひとりに合ったバリアフリー旅行を計画しよう
バリアフリー旅行を成功させるには、事前の情報収集と準備が欠かせません。移動手段や宿泊施設の設備、食事への配慮、体調や障がい特性に応じた行程の工夫など、利用者一人ひとりのニーズに合わせた計画を立てることで、安心で快適な旅行が実現します。
また、万が一の体調不良やトラブルにも備えて、保険やサポート体制を確認しておくことが大切です。バリアフリーへの理解を深めながら、柔軟で丁寧な準備を進めることが、思い出に残る旅の第一歩となります。旅行前に設備や環境を具体的に把握し、利用者目線でチェックを重ねることが、心地よい時間につながるでしょう。